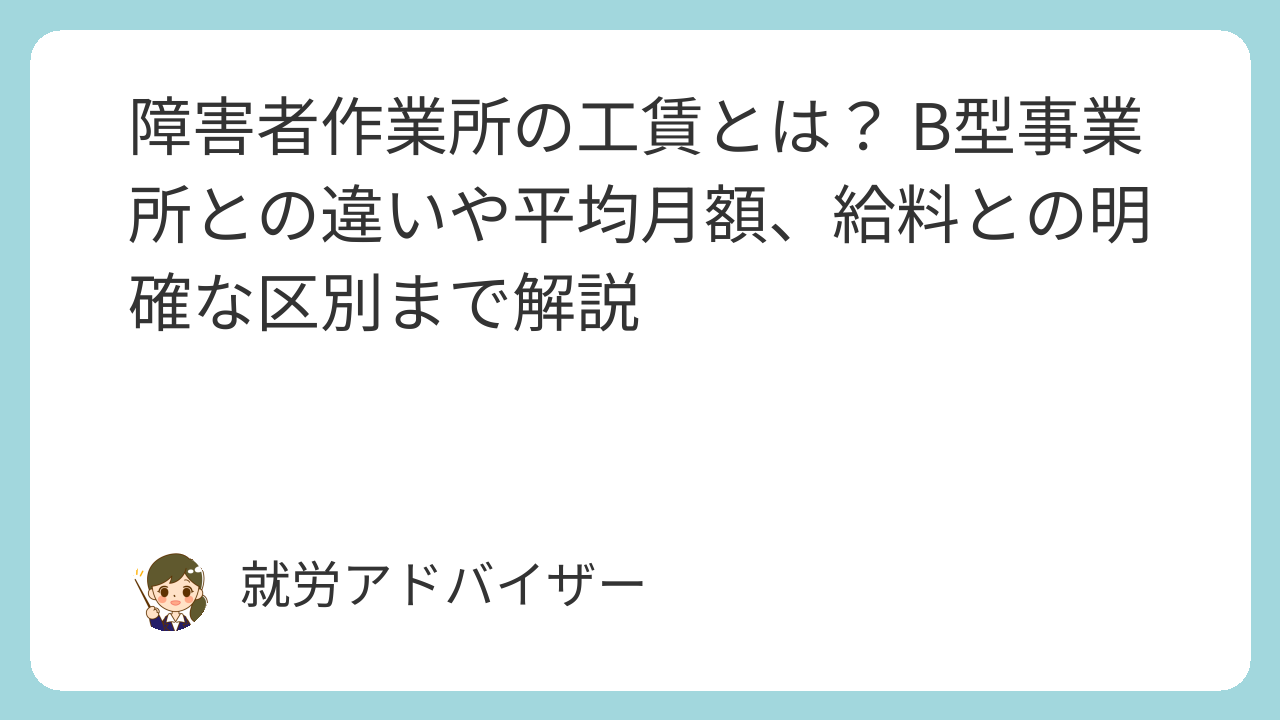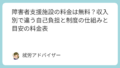福祉関係の施設に関心を持ち始めたばかりの人や、実際に作業所の利用を考えている家族・支援者の「工賃ってそもそも給料と何が違うんですか?」という質問をよく耳にします。
聞きなれない言葉なので戸惑うのも当然ですし、「働くのにお金がもらえるなら給料じゃないの?」と思われる人もいるでしょう
でも実は、法律や制度のうえでは「工賃」と「給料」って、まったく別の仕組みなんです。
知らないまま施設に通所を始めて、「思っていたより金額が低かった…」とショックを受ける方も少なくありません

今回は、この「工賃」とは何なのか、そして「給料」との具体的な違い、さらにはB型事業所・生活介護・就労移行支援との関係まで一つずつ丁寧に整理していきます
なぜ「工賃」という言葉が独立して使われるのか背景を知る
まずはっきりお伝えしておきたいのが、「工賃」とはただの“言い換え”ではないという点です。
単に給料の柔らかい表現というわけではありません⚠️
厚生労働省の資料や福祉現場の制度上、「工賃」とは“雇用契約を結ばずに働いた作業の対価”として支払われるお金と定義されています。
つまり「会社の社員」としての契約がない状態で作業する場合、その報酬は「給料」ではなく「工賃」になるんですね。
代表的なのは、就労継続支援B型事業所です。
ここでは軽作業や製品づくりなどを行い、その対価として工賃が支払われますが、法律上の“雇用関係”が存在しないため最低賃金の適用もありません。
給料と同じように思えて、実は仕組みがまったく違うんです

ちなみに「工賃」という言葉は、障害福祉の分野以外にも、たとえば自動車整備の作業料や内職での報酬など、雇用契約のない作業の対価として幅広く使われている表現なんですよ️
給料との区別が分からないまま通所を始める人が多い理由
「働くのにお金がもらえるなら、それって普通は給料じゃないの?」と思ってしまうのは自然なことです。
実際、制度や仕組みを理解する前に利用を始めてしまい、あとから「思ってたのと違う」と感じるケースはよくあります
その背景には、「雇用契約の有無」や「最低賃金の適用対象かどうか」といった専門的な法律知識が関わってくるため、制度を理解しづらいという問題があります。
とくに就労継続支援B型は「働く」という行為そのものがリハビリや社会参加を目的としている部分が強く、収入よりも“経験を積むこと”を重視している施設も多いんですね。
それでも「時給200円」「月額1万円以下」などの現実を前にすると、納得できないという声も当然出てきます。
SNS上でも、「利用者の作業に対してあまりに対価が低すぎる」「働かせるだけ働かせて搾取では?」という意見が一定数あります。

一方で「社会に出る準備を支援してくれる場所」として前向きに捉える方もいるため、この辺りの認識の差も混乱を生んでいる要因といえます
就労継続支援B型・生活介護・移行支援とのつながりも含めて全体像を把握する
障害のある方の就労支援にはさまざまな施設形態がありますが、混同しやすいのが就労継続支援B型・A型、就労移行支援、生活介護、地域活動支援センターといった種類の違いです。
それぞれ工賃が発生するかどうか、報酬の形態が異なります。
-
就労継続支援B型:雇用契約なし。軽作業を通して生活リズムや働く力を身につける場所。→工賃あり(月1~2万円が相場)
-
就労継続支援A型:雇用契約あり。最低賃金以上の給料が支払われる。→給料制
-
就労移行支援:原則として工賃や給料なし。職業訓練や就職活動がメイン。→一部で工賃を支給する例あり
-
生活介護:介護を中心とした支援。生産活動があれば工賃支給もあり。→工賃あり・なしの施設混在
-
地域活動支援センター:創作・趣味的活動が中心。作業によっては工賃あり。→施設により異なる
このように、報酬の仕組みは通う施設によってバラバラです。
工賃を得たいと思っている場合は、事前に「その施設で工賃が出るか」「どの程度の金額か」を確認しておくのが現実的です
また、支援内容の違いも把握しておくと、自分や家族にとって「何を目的に通うのか」が見えてきます。

ただ単に“お金をもらえるかどうか”で選ぶより、「生活リズムを整えたい」「仕事の練習をしたい」「最終的に就職したい」といった目的に合った施設を選ぶ方が満足度は高くなりやすいです✨
工賃とは何か?|給料や賃金との違いを明確にする
障害者支援の現場でよく使われる「工賃」という言葉は、普段の生活の中ではあまり聞きなれないかもしれませんよね。
「給料」や「賃金」とどう違うのか曖昧なままだと、施設選びや生活設計に影響してしまいます

ここでは、“工賃=雇用契約がない状態で受け取るお金”という基本ルールを軸に、給料や賃金と何が違うのか、どんな仕組みになっているのかをわかりやすく整理していきます
工賃=雇用契約なしで得られる報酬という前提を整理
まず押さえておきたいのが、「工賃」というのは“雇用契約を結ばない形で作業をした人に支払われるお金”という点です。
これは法律の仕組みとして定められていて、厚生労働省の定義でも明確に示されています。
たとえば、就労継続支援B型事業所などでは、作業をしても「労働契約」は結ばれません。
だからこそ、そこでもらえる報酬は「給料」ではなく「工賃」という扱いになります
もう少し具体的にいうと、たとえば週5日、1日6時間働いても、施設とのあいだに雇用契約がなければ「最低賃金」が適用されることはありません。
東京都の最低賃金が1,113円(※2025年6月時点)だとしても、工賃は時給200円前後しかもらえないケースが多いです。
この「雇用関係があるかどうか」が、金額の根本的な違いを生んでいるんですね。
一方、同じように作業しているのに、給料のような扱いを受けられないという現実にモヤモヤしてしまう方も多いと思います。

「ちゃんと作業してるのにどうして?」という感覚はごく自然なもので、現場の当事者だけでなく、その家族や支援者からもよく聞かれる疑問です
賃金・給料と何がどう違うのか具体的に比較
次に、よく混同されやすい「賃金」「給料」との違いについて整理してみましょう
まず「賃金」というのは、労働基準法に基づく言葉で、“雇用契約に基づいて支払われるすべての報酬”のことを指します。
手当や賞与(ボーナス)も含まれるんですね。
そして「給料」というのは、「賃金」のなかでも毎月決まった額として支払われる基本的な報酬を意味します。
つまり、
-
賃金=広い意味での報酬(基本給・手当・賞与などすべて)
-
給料=賃金のうち、主に月給として支払われる報酬
という違いです。
一方、「工賃」はこれらとまったく別枠のもので、そもそも“雇用契約が存在しない”ことが前提になっています。したがって、
-
工賃=雇用契約なしで支払われるお金(最低賃金の適用なし)
-
給料・賃金=雇用契約ありで支払われるお金(最低賃金の適用あり)
という明確な違いがあるわけです。
これは、たとえばバイトで1時間働けば最低でも地域の最低賃金が保証されるのに対し、作業所で働いても1時間あたり200円程度しかもらえない──という差につながってきます。
「え、それっておかしくない?」と感じた方、決しておかしくありません

実際にSNSや掲示板でも「時給200円って何?」「生産してるのに評価されない」といった声が見られますし、行政側でもこの差を埋めるために「工賃向上計画」を全国で推進している背景があります
就労継続支援B型・A型との位置づけの違いもセットで把握
「じゃあ、A型やB型ってどう違うの?」という疑問が出てくるかと思います。

就労継続支援A型とB型の違いを整理しておきましょう
| 比較項目 | A型(就労継続支援A型) | B型(就労継続支援B型) |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 報酬 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(数千円~数万円) |
| 支援内容 | 企業就労に近い働き方 | 自分のペースでの作業 |
| 対象者 | 働ける力がある人 | 働くことに不安がある人 |
一方のA型は、雇用契約を結んで「働くこと」をより本格的に実践する場です。
もちろん、B型から始めて、生活リズムや作業能力が安定してきたらA型へ移行するというルートもありえます。
ただ、そのためには施設の支援だけでなく、本人の希望や体調、そして家族や支援者の理解も大切です
現場では、「B型でもフルタイムで働けるのに、給料じゃなく工賃しかもらえないのがつらい」という声もありますし、逆に「給料がほしいけどA型だと体がついていかない」というケースもあります。

だからこそ、制度の違いを知ったうえで、本人にとって無理のない選択肢を考えるのが現実的なんです。
平均月額と相場|「これだけ?」と感じやすい数字の背景とは
工賃は、通所を検討するうえでかなり気になるポイントですよね
実際に通っている人の声をSNSや掲示板で見ても、「生活費としては全然足りない」「交通費でほぼ消える」といったリアルな意見が目立ちます。
ここでは、「就労継続支援B型」などの主要な福祉サービス別に、工賃の平均月額や相場感をしっかり把握できるように整理していきます。

制度だけでなく、どうして金額にこれほど差があるのか?その背景にも踏み込みます
B型作業所の平均は月16,000円台。最低3000円ルールの存在
まず「就労継続支援B型」の工賃について、厚生労働省の最新データ(令和3年度)によると、全国平均は月額16,507円となっています。
時給換算すると約233円。
都道府県ごとの差はあるものの、これはフルタイムに近い時間で通っている利用者の平均でもこの水準です
しかもこの金額、最低賃金とは無関係です。なぜならB型は「雇用契約なし」が前提だからです。
つまり、1日6時間・週5日働いたとしても、月に1万5千円前後という水準に留まるケースが多いというのが現実です。
とはいえ、あまりにも低い金額を支給している施設ばかりだと問題になります。
そのため、制度上は「事業所全体の利用者の平均工賃が月額3,000円を下回ってはいけない」というルールが設けられています⚠️
ただしこれは“平均値”の話なので、全員が3,000円以上もらえるという意味ではありません。
実際には「一部の利用者だけが高額をもらっていて、他の多くの人は数千円未満」というケースもあります。

工賃はあくまで「作業の成果」に基づく報酬という位置づけなので、作業日数や能力、施設の売上などによって大きくばらつきが出るのが特徴です
就労移行・生活介護・地域活動支援センターの差も一覧で比較
就労継続支援B型以外にも、工賃が発生する可能性がある施設は複数あります。
ただし、すべての施設で工賃が支給されるわけではないという点にも注意が必要です。
以下に、代表的な施設ごとの平均工賃(月額)を一覧でまとめてみました
| 施設名 | 工賃平均(月額) | 工賃の特徴 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 約16,507円 | 全国すべての施設で支給対象 |
| 就労移行支援(工賃あり) | 約18,628円 ※一部 | 工賃があるのは限られた施設だけ |
| 生活介護 | 約3,974円 | 支給なしの施設も多数 |
| 地域活動支援センター | 約8,595円(2013年) | 古いデータながら1万円未満が大半 |
生活介護は「介護中心の支援」がメインのため、工賃のある施設とない施設が混在しています。
厚労省の調査によると、工賃支給ありの施設に限った平均額が3,974円ですが、施設全体のうち約46.3%は月額3,000円未満という調査結果もあります
地域活動支援センターも、平均月額は1万円未満が主流。

創作活動などが中心であるため、生産活動による収益が出にくいという特徴があります
工賃が高い施設・低い施設の具体例を紹介
ただ、実は施設によって工賃額には大きな差があります。
作業内容や経営方針によって月10万円を超えるところもあれば、数千円にとどまるところもあるんです。
▼高工賃の例(※一部引用・再構成)
-
Aさん(B型作業所・東京都)
月額:96,000円
作業内容:農作物の栽培販売/軽作業(ラベル貼り・事務組立など)
週4~5日・1日6時間の勤務 -
Bさん(就労移行支援・一部工賃あり)
月額:40,000円(交通費込)
作業内容:データ入力/名刺作成/フォーム入力など
週5日・1日6時間の勤務
▼低工賃の例
-
Cさん(B型作業所)
月額:8,000円
作業内容:梱包・部品検品・ろうそくの箱詰めなど
週4~5日・1日5時間の勤務 -
Dさん(生活介護事業所)
月額:2,000円
作業内容:清掃/除草/電子機器の分解など
週2~3日・1日4時間の勤務
このように、同じような日数と時間でも、作業の種類や施設の収益力によって何倍もの差が出てしまいます。
特に高額工賃を出せる施設は、製品販売や外部からの受注が安定しているケースが多いです。
一方で、地域や施設規模によってはそもそも売上が少なく、「出したくても出せない」という現実もあります。

こうした課題を改善するために、行政は「工賃向上計画支援事業」を通じて支援しています
→ イチから就職を目指せます!Cocorportの就労移行支援サービス
工賃の作業内容と金額例|頑張っても給料並にはならない?
フルタイムに近い日数と時間で働いても、月額1万円以下の工賃しかもらえないケースは普通にあります。
それに対して、同じB型事業所でも月10万円を超える工賃を支給している施設も存在していて、その差に驚く方も多いです。

ここでは、「どんな作業をしたら工賃が出るのか」「なぜ同じ時間働いても差がつくのか」「施設選びで見るべきポイントは何か」を掘り下げていきます
ケーキづくり・清掃・野菜栽培などのリアルな作業と時給の関係
まず、工賃が発生する「生産活動」にはどんな種類があるのかというと、けっこう幅広いです。
以下のような作業がよく見られます
-
焼き菓子(クッキー・マフィン)などの製造・販売
-
オフィスビルや公園などの清掃作業
-
野菜や花の栽培と販売
-
自動車部品や電子機器の組み立て
-
アンケートやフォーム入力などのデータ処理
-
雑貨・キャンドル・布小物などの制作と委託販売
作業は施設によって異なりますが、いずれも「売上を生み出せる活動」である必要があります。
売上がある=報酬(工賃)として利用者に還元できるという仕組みなんですね。
ただし問題は、どの作業も「内職に近い単価」であること。
たとえば清掃作業で1時間がんばっても、施設全体の契約金額から経費が引かれて、個人の取り分は時給200円前後というケースもあります。
たとえフル稼働しても最低賃金に届かない…という現実があります
一方で、野菜や手作り品の販売を直営で行っている施設や、企業と外部契約して業務受託をしている施設では、比較的高めの工賃を設定している場合もあります。

その差が「施設の工賃ランキング」などでも可視化されてきています
同じ時間でも施設により月額10万円と2,000円の差がある理由
これはとても大事な視点なのですが、「働いた時間」ではなく「施設の経済力と仕組み」によって工賃が決まるという点が、工賃制度の最大の特徴です。
例えば、AさんとBさんがともに「週5日、1日6時間」で通所していたとしても、以下のような差が起こり得ます。
-
Aさん:時給換算400円、月額96,000円(自社ECで野菜・クッキー販売)
-
Bさん:時給換算70円、月額8,000円(地域からの清掃受託のみ)
この違いを生んでいるのは、「どれだけ売上があるか」「どんな事業モデルを採用しているか」なんです。
つまり、個人の頑張りだけではどうにもならない領域があるということなんですね。
実際、厚生労働省の調査でも「施設ごとに最大で月8~9万円の工賃差がある」とされています。

同じ制度のなかにいても、立地や業務受託の有無、販売ルートの確保によってここまで大きく違ってしまうというのは、見落とされがちな現実です。
施設選びで重視すべき「生産活動の質」と「経営力」の重要性
じゃあ、「工賃が多くもらえる施設に行けばいいのか?」と言われると、話はそんなに単純ではありません
工賃の高い施設は、たしかに売上が出せる仕組みを持っています。
ですがその一方で、「販売ノルマに近いプレッシャーがある」「職員が忙しくて支援が手薄になる」「事業としての成果が求められ精神的にしんどい」といった側面もあります。
一方で、工賃が少なくても「居場所としての安心感がある」「マイペースに続けられる」「人との関わりが丁寧」という理由から選ばれる施設もたくさんあります。
つまり、“何を優先するか”によって、理想の施設像は変わるということです
それでも「ある程度の金額がほしい」「将来的に自立を目指したい」という希望があるなら、以下のポイントはチェックしておくといいでしょう
-
生産活動の内容にバリエーションがあるか?
-
自社製品の販売や委託業務があるか?
-
外部企業との提携実績があるか?
-
工賃実績を毎年公開しているか?
-
工賃向上計画を施設HPで公表しているか?
これらは、「その施設が経営視点でも頑張っているか」の目安にもなります
施設の見学時には、「ここではどういう作業がありますか?」「工賃は平均でどれくらいですか?」といった質問を率直にしてみて下さい。

答え方に濁りがないか、具体例を出してくれるかも大事なチェックポイントになります。
SNSや掲示板で見かけたリアルな声|「少なすぎて生活できない」
制度や法律の話をどれだけ正確に伝えても、最終的に人の心を動かすのは、リアルな声や現場での実感です
ここではX(旧Twitter)や5ちゃんねる、知恵袋、noteなどのプラットフォームに投稿された「工賃」に関する生の意見を取り上げながら、制度への違和感や共感、そして一部の“逆の視点”も交えて整理していきます。

同じ制度のなかにいても、感じ方や価値観には大きな幅がある──そんな現実が見えてきます。
「なんで最低賃金が適用されないの?」という素朴な不満
PREP法でいうと、まずポイントは「多くの人が“なぜ最低賃金がもらえないのか”という疑問を抱いている」という点です。
その理由としては、「毎日通って働いているのに、普通のバイトとは違って賃金保障がない」という制度的なズレがあるからです。
実際、掲示板やSNSではこんな投稿が目立ちます
「娘がB型作業所に通っていて、月1万円ちょっと。でも週5日フルで働いてるのに…。時給換算したら数百円にも満たない。どうしてこれが許されるの?」(知恵袋)
「バイトなら最低でも時給1,000円あるのに、B型は時給200円以下。障害があるだけで、こんなに扱い違うの納得いかない」(X)
制度上、「雇用契約がない=最低賃金が適用されない」というルールがあるといっても、それを事前に知らされていなかったり、納得できる形で説明されていなかったりすると、こうした疑問や怒りは起こりやすいんですね

また、「働く=生活費を得る手段」と考えている方からすると、工賃だけでは家賃や食費すら賄えないという現実も、「生活できない」という直接的な不満につながりやすいです。
「時給200円で働かされてる感覚」SNS上の実例を引用
次に、工賃の“少なさ”だけでなく、「働かされている感覚」や「不当な労働」という捉え方に近い声も見かけられます。
PREPでいえば、感情の高まりが制度批判に直結しているのがこのパターンです。
理由は、支援の場であるはずの作業所が「利益だけを追求して利用者を搾取している」と感じてしまう構図が見えてしまうためです。
たとえばSNS上では、こんな投稿がシェアされています
「B型で週5勤務。朝9時~15時まで作業して、もらえるのは月7,000円。1時間働いても100円ちょっと。これってどう考えてもおかしいと思う」(X)
「納期に追われてガチ作業させられてるのに、時給200円。職員は正社員で給料もらってるのに、こっちはなんなの?ってなる」(note)
もちろん、こうした施設が全体の多数派とは限りません。

ですが、利用者側に「働かされている」と感じさせるような空気がある場合、工賃の額以上に不信感や失望が積み重なりやすくなります
逆に「やりがい重視で満足」と語る人も|感情ベースの主観を比較
一方で、全員が工賃の金額に不満を抱いているわけではないという事実もあります。
これは“何を目的に通っているか”によって、感じ方がまったく違うからです。
PREPの視点で整理すると、ポイントは「工賃が低くても満足している人も存在する」という点で、それは「働く場所がある」「社会との接点が持てる」といった感覚から来ています。
たとえば、こういう声もあります
「以前は家にひきこもっていたけど、B型作業所に通うようになって生活にリズムが出てきた。工賃は少ないけど、外に出るきっかけになったのが大きい」(5ちゃんねる)
「ここで作ってるクッキーが地元のイベントで売れて嬉しかった。“自分にもできることがある”って感じられたのが何より大きかった」(note)
このように、金銭的な評価軸よりも、「やりがい」「つながり」「居場所感」を重視する利用者にとっては、工賃は“おまけ”に近い感覚というケースもあります
ただしこれは、「金額が低くても気にするな」という話ではありません。

「人によって重視するものが違う」という視点を持つことで、制度をどう改善していくべきかを考えるヒントにもなります
工賃と税金・確定申告の話|年収いくらから必要になるのか
工賃の金額が少ないとはいえ、「税金ってどうなるんだろう?」「確定申告は必要なのかな?」と不安になる方も多いです
特に、扶養に入っている場合や、他にアルバイトや副業をしている人は、申告の有無が気になるところですよね。

ここでは、工賃が課税対象になるかどうかの基本ルールから、副収入との組み合わせによる注意点、そして実際に迷ったときの相談先まで、しっかり丁寧に整理しておきます
工賃にも課税されるの?103万円ルールと雑所得扱いの整理
最初に押さえておきたいのは、「工賃=非課税」ではないという点です。
よく誤解されるのですが、工賃も原則として課税対象になります。
ただし、課税されるかどうかは「年間の合計所得」によって決まるんです。
工賃は「雇用契約がないため、給与所得ではなく“雑所得”として扱われる」ことが多いです。
この“雑所得”は、他の収入(給与・事業所得など)と合算して、年間の所得が103万円を超えた場合に、所得税が発生します。
つまり、年間103万円以内であれば、基本的に確定申告は不要で税金もかからないということになります
これは主婦や学生の「扶養内での収入」と同じルールですね。
多くのB型作業所では、月額1~2万円程度の工賃が一般的なので、年間で103万円を超えることはほとんどありません。
したがって、多くの利用者は「申告しなくてOK」という結論になる場合が多いです。

ただし、収入が多かったり、ほかに副業収入がある場合は話が変わってきますので、次の項目で詳しく見ていきましょう。
給与や副業と合わせたときの申告要否の判定方法
「普段はB型作業所に通って工賃をもらってるけど、時々短時間のバイトもしてる」「YouTubeやメルカリでもちょっと収入がある」──こういったケース、意外と増えてきてます
このように、工賃以外にも所得がある場合は、すべての収入を合計して確定申告が必要かどうか判断する必要があります。
判断のポイントは、以下のような点です
| ケース | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 工賃のみで年収80,000円 | 不要(課税対象にならない) |
| 工賃+給与あり(合計年収120万円) | 原則必要(源泉徴収の有無により異なる) |
| 工賃+メルカリ収入50,000円 | 要注意(収入内容によっては申告対象) |
| 工賃+障害年金受給 | 原則不要(年金非課税+工賃が少額なら) |
ちなみに工賃は、一般的に源泉徴収票も年末調整も発行されないことが多く、自分で収支を記録しておく必要があるという点も注意が必要です。

帳簿をつけるほどではなくても、ノートやスマホアプリで月ごとの収入メモをつけておくと、申告時に慌てずに済みます
「確定申告ってどうするの?」と迷ったときの具体的な相談先も紹介
「申告が必要かもって言われても、実際どうやればいいのか分からない…」と感じる方、多いと思います
そんなときに相談できる場所はちゃんとありますので、安心して下さいね。
以下に、おすすめの相談先をまとめました
税務署(最寄りの管轄)
→ 確定申告の相談窓口が設置される時期(2月〜3月)は、丁寧に教えてくれます。電話予約も可能です。国税庁の公式HPからも管轄検索ができます。
市区町村の障害福祉課 or 福祉相談窓口
→ 工賃や障害年金に関する税務の相談も受けてくれます。地域によって対応が異なるので、事前に電話で確認するのがおすすめです。
就労支援事業所のスタッフ
→ 経験豊富な支援員さんがいるところでは、「前年の収入の集計の仕方」や「どこに行けば申告できるか」まで教えてくれます。
無料税務相談(全国の税理士会)
→ 2月〜3月の時期には、全国の税理士会が無料相談会を実施しています。障害者や高齢者のためのサポートも強化されています。

これらの相談先をうまく活用することで、「知らなかったから損した」というリスクを減らすことができます
工賃向上計画と規程|行政や施設がどこまでやっているのか?
ここまで読み進めてきた方なら、「工賃ってどうやって決まってるの?」「施設によって差があるのはなぜ?」という疑問が出てくる頃かもしれません
実は、障害者支援施設における工賃には、それぞれ施設独自の“工賃規程”があり、さらに国(厚生労働省)からは“工賃向上計画”という取組みが求められています。
どちらも聞きなれない言葉かもしれませんが、工賃の金額や仕組みに大きく関わっている大事なポイントなんです

ここでは、「規程って何が書いてあるの?」「計画は形だけじゃないの?」といった疑問に、具体例も交えながらわかりやすく解説していきます。
工賃規程は施設ごとに存在。支払い日・金額の決まり方も明記
まず押さえておきたいのが「工賃規程」という存在です。
これは、簡単にいうと“施設がどのようなルールで工賃を決めているかを明文化した書類”です
厚労省の定めによって、就労継続支援B型や生活介護などで工賃を支払う場合は、施設ごとにこの「工賃規程」を整備しておくことが義務付けられています。内容としてはこんな項目が含まれています
-
工賃の計算方法(出来高制 or 時間給制など)
-
支給日(月末締めの翌月15日など)
-
支給方法(現金手渡し or 銀行振込)
-
欠勤や早退があったときの減額ルール
-
施設外就労・在宅支援の工賃の扱い
こういった内容がしっかり書かれていないと、トラブルの原因になり、行政の実地指導(=監査のようなもの)でも指摘を受けてしまいます
利用者としても「今月の工賃、何でこんなに少ないの?」とモヤモヤしないために、入所前や契約時にこの工賃規程をよく読んでおくことが重要です。

納得いかない点があれば、スタッフに遠慮せずに確認してOKです
工賃向上計画とは?厚労省主導の背景と今後の方針
次に紹介するのは「工賃向上計画」という取り組み。
これは厚生労働省が2007年度から始めた、全国の作業所の工賃を少しでも引き上げていくための制度的な枠組みです
なぜこんな計画が必要なのかというと、「時給200円未満」「月額数千円」という現状があまりにも厳しいから。
障害者が地域で安定して暮らすには、工賃だけでなく障害年金や各種手当の組み合わせが必要ですが、それでも「工賃の底上げ」は急務という課題があるんですね。
実際の取り組みとしては、各事業所が3年ごとに「工賃向上計画書」を作成し、以下のような内容を国または都道府県に提出します
-
現在の工賃額と推移
-
今後3年間の目標額(たとえば+3,000円など)
-
工賃向上のために取り組む内容(商品開発・販売チャネルの拡大・業務提携など)
-
成果指標やスケジュール
この取り組みは義務ではありますが、実際に補助金や支援制度とセットになっているため、「ちゃんと作って、ちゃんと実行すれば支援が得られる」という現実的なメリットもあります

ただし問題は、「計画を作ることが目的化してしまう施設」も少なくないという点です。
施設が目標額を設定していても現実とのギャップが大きいケースも
「工賃を増やしたい」「少しでも生活の足しになるようにしたい」──これはほとんどの事業所が共通して持っている思いです。
でも、現実として“計画通りに上がらない”という施設も多いのが実情です。
SNS上や当事者ブログでは、こんな声が上がっています
「工賃向上計画って何のためにあるの?うちの施設、3年前からずっと『月額2万円を目標』って言ってるけど、実際は1万円前後のまま。職員も変わらないし、仕事内容も変わってない」(X)
「計画書を見せてと言ったら、“職員しか見れません”って言われた。何かおかしくない?」(note)
たしかに、施設の規模や立地、職員のスキル、商品販売の難しさなど、さまざまな制約があるのは事実です。
たとえば、地方で販売ルートが確保できない施設や、施設内の高齢化が進んで生産効率が下がっている場合、どんなに努力しても“売上=工賃”は伸びづらいという現実もあります。
また、「工賃向上にばかり力を入れて、福祉的な支援がおろそかになっている」という批判が出るケースもあり、バランスの難しさが課題となっています。
だからこそ、見学の際には「工賃向上計画はどんな内容ですか?」「具体的な取り組みは何かありますか?」といった質問をしてみるのがおすすめです

答えが明確で、実際の取組み内容を丁寧に話してくれる施設は、利用者への誠実さや経営意識が高いといえるでしょう。
よくある質問
ここでは、「障害者 作業所 工賃」関連で検索されやすい言葉をもとに、利用者やそのご家族、支援者の方から寄せられるよくある疑問や不安の声をまとめてお答えしていきます

Googleの検索キーワードにも出てくるような現場で“本当に聞かれること”を中心に取り上げていますので、「あ、それ気になってた」と思った方はぜひチェックしてみて下さいね。
Q1. 工賃と給料はどう違うんですか?
工賃は“雇用契約がない”作業に対して支払われるお金で、就労継続支援B型などで支給されます。
一方、給料は“雇用契約がある”働き方に対して支払われるもので、A型事業所や一般企業での勤務が該当します。
工賃は最低賃金の対象外で、月額1~2万円程度が相場です。
Q2. B型作業所の工賃って安すぎませんか?
安いと感じるのは自然なことです。実際、全国平均でも月16,000円ほどとされています(令和3年度)。
作業量や時間に見合わないと感じる方も多く、SNSでは「時給200円以下」といった不満も目立ちます。
Q3. 工賃だけで生活できますか?
結論から言うと生活するのは難しいです。
工賃はあくまで“作業の対価”であり、生活費として十分な金額ではありません。
そのため、多くの方は障害年金・生活保護・家族支援と組み合わせて生活しているケースがほとんどです。
Q4. 工賃って確定申告が必要なんですか?
年収103万円以下なら申告は不要です。
ただし、給与や副業と合わせて103万円を超える場合や、扶養判定が関係してくる場合は申告が必要になることがあります。
基本的には“雑所得”として扱われるケースが多いですが、不明な場合は税務署や福祉課に相談するのがおすすめです。
Q5. 高い工賃を出してる施設ってどうやって選べばいいの?
工賃が高い施設は、販売力・経営努力・地域との連携が強い傾向があります。
見学時に「工賃平均額は?」「何を作って販売していますか?」といった質問をして、実際の数字や活動内容を確認しましょう。
また、「工賃向上計画」の中身を聞くのも目安になります。
Q6. 施設によって工賃の差が大きいのはなぜですか?
主な理由は、作業の内容と収益性の違いです。
自社製品をオンライン販売している施設や、企業から仕事を受託している施設は、比較的高い工賃を実現しやすいです。
逆に、内職や清掃など単価が低い仕事がメインの施設は、どうしても支払える工賃が限られてしまいます。
Q7. 工賃が未払いになることってありますか?
本来は工賃規程に基づいて毎月きちんと支払われるのが原則ですが、経営が厳しい施設では支給が遅れたり、未払いが発生するケースもあります。
支払日を過ぎても振り込まれない場合は、市区町村の障害福祉課に相談しましょう。
「給付金から工賃を出してはいけない」というルールもあり、資金繰りが難しい施設も少なくありません。
Q8. 工賃を上げてもらう方法ってあるんですか?
利用者個人が直接金額交渉するのは難しいですが、施設全体の売上が上がれば工賃も上がる仕組みになっています。
そのためには、商品やサービスの改善提案・生産性の向上・新たな販売ルートの開拓などが求められます。施設が「工賃向上計画」に本気で取り組んでいるかが、長期的には重要な判断軸になります。
まとめ|「工賃」で暮らすという現実をどう受け止めるか
ここまで「工賃とは何か」「給料とどう違うのか」「金額の相場や施設ごとの違い」「SNSの声」など、さまざまな角度から解説してきました。
読み進める中で、「思っていたより厳しい」「やっぱり生活は難しそう」と感じた方も多いと思います
でも同時に、「そもそも工賃ってどんな位置づけなのか」「どう向き合えば無理なく前に進めるのか」まで整理できていれば、このテーマに対する不安やモヤモヤは少しずつ和らいでいくはずです
工賃は報酬ではあるが「生活費としては不十分」という現実
まず前提として、工賃はあくまで“作業への対価”であり、生活費をまかなうレベルには達していないという現実があります。
これは厚生労働省のデータを見ても明らかで、就労継続支援B型の全国平均は月16,000円台にとどまっています。
つまり、「工賃=収入」ではあるけれど、「工賃=生活を支える柱」ではないという立ち位置です。
通所日数を増やしたり、作業の質を上げたりしても、限界があります。
SNSなどでも「がんばっても生活費にはならない」「交通費と昼食代で消える」という声が多く、報酬としての“期待値”が高すぎると、現実とのギャップに苦しみやすくなります
支援制度や年金との併用を前提に考えるのが現実的
だからこそ、「工賃だけで生活する」のではなく、障害年金・生活保護・各種手当・家族からの援助などと組み合わせて生活設計することが大前提になります。
たとえば障害年金(2級)の受給者であれば、月額6万〜7万円程度が支給されるケースが多く、これに工賃を合わせて「月8万〜9万円程度」が生活資金のベースになります。
そこに加えて、住居費を抑えた地域支援住宅やグループホームなどを活用することで、実際に“生活していける”環境を整えることは可能です
行政窓口や就労支援の相談員、家族などと一緒に、「どの制度が使えるのか」「今の収入状況でどこまで申請できるか」を整理する時間はとても大切です。

逆にこの整理をしないまま、「なんとなく」で通い始めると、後から「こんなに少ないなんて聞いてない」と感じてしまいがちです。
工賃だけを頼りにせず、支援のステップとして捉える視点も必要
最後に大事なのは、工賃を「生活を支える柱」として見るのではなく、「社会とつながる第一歩」として捉える視点です
もちろん、金額の少なさにがっかりしてしまう気持ちは自然なものです。
でも、B型作業所や生活介護などは、働くリズムを身につけたり、社会参加の場を作ったりする“土台”としての役割があります。
ある利用者の言葉が印象的でした。
「はじめは時給200円にショックを受けたけど、それでも“ありがとう”って言ってもらえたのが嬉しかった。人と話せるようになって、将来バイトにチャレンジする気持ちが芽生えた」
金額だけを見て判断してしまうと、本来その人にとってプラスになる環境が見えづらくなります。
「通う目的は“お金”だけじゃない」という感覚を持つことで、ストレスも少し軽くなります✨
もちろん、施設の経営努力によっては、しっかりとした工賃を出せるところもあります。
そういう施設を探したい方は、「工賃向上計画の内容を開示しているか」「販売力や外部連携があるか」などを確認して選んでみて下さいね。
おわりに…
「工賃だけじゃ生活は無理」──それはたしかに現実です。
けれど、無理だからといって絶望する必要はありません。
制度をうまく使いこなしながら、できることを少しずつ増やしていく。
その過程で自信が生まれたり、新しい選択肢が見えてきたりするんです。
焦らず、比べず、自分のペースで取り組んでいけばいいと思います

疑問や不安があれば、専門機関や支援者に相談してみて下さいね