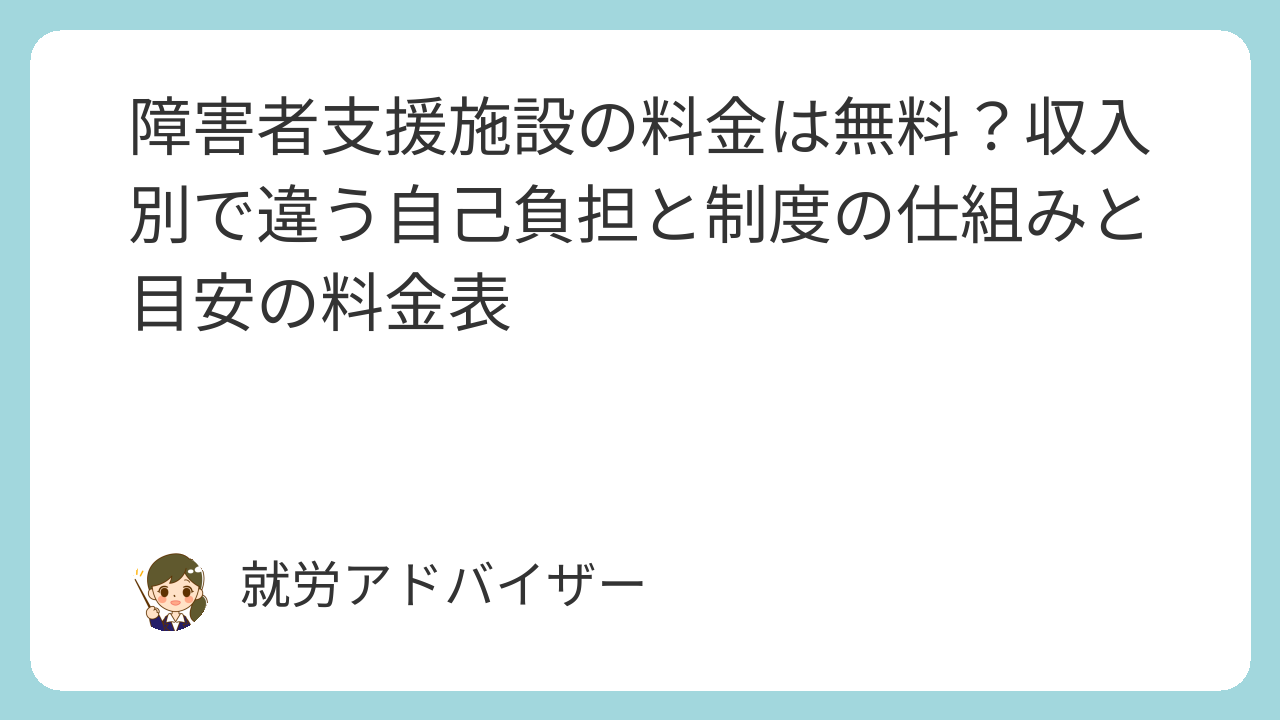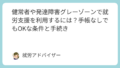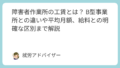障害者支援施設を利用するうえで、最初に気になるのが「どれくらい費用がかかるのか?」という点だと思います。
誰でも通えるわけではないという制限だけでなく、自己負担額にもいろいろな条件がついていて、正直ちょっとややこしい印象を受けた方も多いはずです。
結論から言えば、障害福祉サービスは収入によって利用料が変わる仕組みになっていて、なんと9割以上の方が自己負担ゼロで使えているという現実があります。
ただしそれは「自動的に無料になる」わけではなく、条件を知らずにいると「無料のはずが有料になっていた」というケースも見られます。

今回は、初めて障害福祉サービスを使う方や「手帳がないけど使えるのかな?」と感じている方向けに、誤解のないように丁寧に料金の仕組みをお伝えしていきますね。
障害福祉サービスの「料金」がわかりにくい理由
障害福祉サービスは、国・都道府県・市区町村が一体となって提供しているため、関わるルールや制度が多くなりがちです。
また、「支援施設ごとに違う1日の利用料金」や「所得に応じた月額上限額」など、複数のルールが同時に適用されるため、慣れていない人にとっては全体像がつかみにくいのも正直なところです。
しかも「障害者手帳があれば無料」というわけでもなく、「手帳がなくても無料になるケース」もあります。

このへんが余計に混乱を招いている原因なんですよね。
制度が複雑すぎて「無料」の条件が見えにくい
多くの人が誤解しているのが、「住民税非課税世帯=自分も無料」という思い込みです。
実際には「誰が世帯に含まれるのか」「何をもって収入とするのか」によって結果が変わります。
例えば、20歳を過ぎた子どもが親と同居していても、世帯としては「本人のみ」と判断されることもあれば、逆に「親の収入も世帯収入として合算される」こともあるんです。

自治体ごとに運用のルールも違うので、ネット情報だけでは判断しづらいという声が多くあります。
利用料金の仕組みは「1割負担」が基本
障害者支援施設を利用する料金は「サービス費の9割を国や自治体が出してくれるから、利用者は1割だけ払えばいい」という仕組みです。
つまり、サービスの全額を払うわけではないということなんですね。
それだけでもハードルがグッと下がった気がしませんか?
ただし「1割」と言っても、実際にいくら払うのかは利用する施設や日数によって変わってきます。

ここでは、その内訳や考え方を具体的にお伝えしますね。
サービス費の9割は国と自治体が負担️
障害福祉サービスは「公的な支援制度」です。そのため、利用料金の大部分を国と自治体が支えてくれています。具体的には、サービス費用の9割が公費でまかなわれ、残り1割を利用者が支払うかたちになっています。これが「1割負担」という基本の考え方です。
つまり、1日あたりのサービス費が仮に1万円だったとしても、実際に利用者が払うのは1,000円。とても大きな支援ですよね。
利用者が払うのは「1日の利用料×日数」
次に気になるのが「じゃあ、結局いくら払うの?」という話です。基本的には1日の利用料金に通所した日数をかけた金額が、月の支払い額になります。
たとえば、1日あたりの利用料が1,000円の施設に月15日通うと、1,000円 × 15日 = 15,000円。ですがここで「月額の負担上限額」が登場します。収入によってこの上限が設定されていて、たとえば9,300円が上限なら、15,000円の請求でも9,300円しか払わなくていいというわけです。
1日の料金は事業所によって違う
実はこの「1日あたりの利用料」は全国一律ではありません。サービス内容や運営体制、地域の事情などによって、事業所ごとに金額が違うんです。
たとえば、就労移行支援だと1日500円~1,300円くらいが相場ですし、就労継続支援B型だと500円~700円くらいのところもあります。同じ種類のサービスでも金額にばらつきがあるため、気になる施設があれば事前に確認しておくと安心です。

施設のホームページに載っていないこともあるので、見学の際に「1日の利用料はいくらくらいですか?」と直接聞いてみるのが一番確実ですよ✨
利用料が無料になる人の条件✨
障害福祉サービスを、9割以上の人が“無料”で利用しているというデータは意外に知られていない事実です。

ここでは、どんな人が無料対象になるのか、その条件について詳しくご説明していきますね。
市町村民税非課税世帯なら「0円」
まず、もっとも多いのが「市町村民税が非課税になっている世帯」です。
この世帯に属する人は、基本的に利用料が0円になります。たとえば、本人が障害年金で暮らしていたり、世帯の収入が低かったりする場合ですね。
ここで言う「非課税世帯」とは、単に本人だけの収入ではなく同じ家で暮らしている家族全体の課税状況をもとに判断されます。なので「親と同居している場合」などは、親の収入が影響してくる点に注意が必要です。
生活保護を受けている世帯は完全無料
もし、生活保護を受けている方であれば、すべての障害福祉サービスが無料になります。これはもうルールとしてバッチリ決まっているので、特別な手続きや条件確認は不要です。
生活保護世帯の方は、どんな支援サービスでも「負担上限額0円」が適用されるため、通うたびにお金がかかる心配はありません。就労移行支援でも、生活介護でも、必要な支援を安心して受けられるのは心強いですね。
年収によって上限額が決まっている理由
ここまでで「非課税なら無料」という話をしましたが、じゃあ「課税されている人は全員高額負担なの?」と思った方、安心してください。実は課税世帯でも「自己負担の上限額」が決まっているんです。
たとえば、年収に応じて以下のような上限が設定されています:
-
年収が低めの課税世帯 → 月額9,300円
-
さらに高い課税世帯 → 月額37,200円
この「月ごとの上限」があるおかげで、利用日数が多くてもそれ以上の金額は発生しません。だから負担が青天井になることはないんです。
つまり、障害福祉サービスは「収入に応じて利用しやすくする仕組み」がちゃんと整っている制度なんですね。
無料で使えるかどうかを知っておくことで、金銭的な不安なく支援を受ける選択肢が増えるのは大きなメリットです。

気になる方は、まずはお住まいの市区町村に問い合わせてみましょう
年収別の自己負担上限額を一覧で確認
障害福祉サービスを利用するとき、どれだけ使っても「ある一定の金額以上は支払わなくていい」という月額上限が決まっています。
これが「自己負担上限額」というルールです。
この上限のおかげで、利用回数が多い人ほどお得になるという仕組みになっているんですよ。

ここでは「年収別にいくら払うことになるのか」を分かりやすくまとめていきますね。
「一般1」「一般2」の違いは何か?
自己負担上限額には「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」といった区分があります。特にややこしいのが「一般1」と「一般2」の違いですが、ここを押さえておくとスッキリ理解できます。
-
一般1:住民税課税世帯だけど、所得が一定以下(18歳以上なら市町村民税所得割16万円未満など)
-
一般2:一般1よりも収入が多い世帯(それ以上の所得がある)
この2つの違いによって、月にかかる最大の利用料が変わってくるんですね。
年齢・家族構成によっても上限は変わる
じつは、この上限額は本人の年齢だけでなく、家族の構成や収入によっても変わります。
例えば…
-
18歳未満の場合:月額4,600円で済むケースあり(通所型など)
-
18歳以上で親と同居:親の収入も判定に含まれるので注意
-
一人暮らし:本人の収入だけで判断されるため、無料になりやすいケースもあり
つまり「自分が働いていないから0円かな?」と思っていても、世帯全体の課税状況で判断されることもあるので、油断せず確認することが大事です。
「9,300円で頭打ちになる人」とは?
「頭打ち」っていうのは、いくらサービスを使ってもそれ以上は払わなくていいという意味です。
たとえば…
-
就労移行支援:1日1,000円×15日=15,000円
でも、上限が9,300円なら実際の支払額は9,300円でOKというわけです。
この9,300円の上限が適用されるのは、先ほど説明した「一般1」の人たちです。つまり「課税世帯だけど、そこまで高収入ではない」という層ですね。
逆に「一般2(上限37,200円)」になると、かなりの負担になるため、支援を続けていくかどうかは検討が必要になるかもしれません。
上限額があるおかげで、障害福祉サービスは思っているよりずっと手の届く支援になっています。

「なんとなく高そう」と避けてしまう前に、自分の区分や上限額をチェックして、安心して使える制度をしっかり活用していきましょう
自分の料金を試算する方法
実際に、「自分はいくらかかるの?」「無料になるのか不安…」という方は多いと思います。
でも安心して下さい。
実は、ネット上で簡単に試算できるツールがあるんです。
「負担額シミュレーター」や「料金計算ツール」といった名前で公開されているサイトがあるので、それを使えばたった数分で自分の月額負担額の目安がわかります。

ここでは、使い方や注意点をわかりやすく解説していきますね。
オンラインの負担額シミュレーターを使う
最近では、多くの自治体や支援サイトで「利用者負担額の自動計算ツール」を提供しています。自分の住民税額や世帯の収入状況を入力すれば、「月額0円」「上限9,300円」「上限37,200円」などの結果がすぐ出るんです。
使い方の例としては…
-
自分の住民税額を確認(または「非課税」などを選択)
-
世帯の人数と収入を入力
-
利用する支援サービスの種類を選ぶ(例:就労移行支援)
結果が表示されるので、自分がどの区分に入るのかすぐにわかります。
一部のツールでは、過去の確定申告書や課税証明書が必要になることもありますが、今すぐの目安としてはかなり便利ですよ
計算に使う「世帯収入」の範囲を間違えない
ここが要注意ポイントです。
よくある誤解として、「自分の収入だけで判断される」と思ってしまう人がいます。でも、障害福祉サービスの負担額は世帯全体の市町村民税額をもとに計算されるんです。
たとえば…
-
実家暮らし:両親の収入が判定対象になる
-
結婚している:配偶者の収入も見られる
-
一人暮らし:本人の収入だけが対象になるので無料になりやすい
つまり「自分は無職だから無料になる」と思っていても、親や配偶者の収入が多ければ、上限が9,300円や37,200円になる可能性もあるということですね。
よくある「親と同居=無料じゃない」勘違い
とくに20代前半で実家暮らしをしている方に多いのが、「自分が収入ないから無料だよね」という勘違いです。
実際には、同じ世帯の家族の市町村民税額も含めて判定されるので、親が高収入の場合は「一般2」扱いになり、月額37,200円かかることもあります。
親の扶養に入っているかどうかだけではなく、「住民票上の世帯」として一緒になっているかどうかも影響します。
逆に「自分だけ別世帯になっている」「一人暮らしをしている」場合は、かなりの確率で月額0円または上限9,300円で済むというケースもありますよ。
以上の点をふまえて、まずはオンラインのシミュレーターを使ってみるのが安心です。
迷ったら、地域の障害福祉課や支援センターに相談すれば、具体的に教えてもらえます。

最初はちょっと面倒に思えるかもしれませんが、「実は無料で使える支援だった」というケースも多いので、ぜひ試してみて下さいね
利用料以外にかかる費用もチェック
ただし、注意点として施設の利用料以外にも「思わぬ出費」があるというケースは少なくありません。

そういった“見落としがちなポイント”までしっかり把握して、損なく支援を受けましょう。
昼食代・交通費・医療費などの実費負担
まず多くの施設で共通してかかるのが「昼食代」と「交通費」です。
たとえば、毎日お昼ご飯を支給している施設でも「昼食代300円/日」という形で別料金になっているケースが多いです。月に15日通えば、それだけで4,500円くらいになることもありますね。
さらに、交通費も意外と負担になります。自宅から遠い施設だと、1日往復で数百円、月に数千円の出費になることもあります。特に電車やバスで通う方は注意が必要です
そしてもうひとつ見落としがちなのが「医療費」。
たとえば、就労支援に通うことで通院頻度が増えたり、定期的なカウンセリングを受けるようになった場合、その医療費は当然自己負担になります。支援サービスとは別枠です。
支援内容によって「別料金」がかかることも
事業所によっては、特殊なプログラムを導入している場合や、教材費・制服代・作業着費用などが発生するケースもあります。
たとえば…
-
eラーニングの教材費(1,000〜3,000円)
-
作業に使うエプロンや上履きなどの購入費(2,000円前後)
-
外出訓練などでの交通費や施設利用料(実費)
といった具合です。
施設のパンフレットやWebサイトには記載がなかったとしても、見学時や契約前の説明会で「実は別料金がある」と伝えられるケースもあります。
減免制度・自治体の補助でカバーできる例
ただし、そういった実費も「自己負担確定」と思うのは早いです。
多くの市区町村では、交通費補助や昼食費の助成制度が用意されています。実際、「月上限3,000円まで交通費補助あり」「昼食代は自治体の負担で0円」という事業所も存在します。
さらに生活保護を受給している方、もしくは住民税非課税世帯の方は、補助対象になるケースがかなり多いです。
また、障害者手帳を持っていれば公共交通機関の割引が使えることもあり、定期券やバスの回数券が半額になるなど、知らないと損する制度も意外とあるんです
見学や体験利用の際には「利用料は無料になるか?」だけでなく、「昼食代や交通費はどうなっていますか?」と聞いてみるのがおすすめです。
そして、市区町村の福祉課にも「支援施設の実費負担に関する助成制度はありますか?」と確認してみましょう。
利用者の中には、「無料だから安心」と思っていたのに、あとから細かい出費が積み重なって、思ってたより負担が大きかった…という声もあります。

だからこそ、最初の段階で「トータルの支出」をしっかり把握しておくことが、安心して長く支援を受けるためのコツです
SNSや体験談で広がるリアルな声
支援施設の料金については、公式サイトやパンフレットだけでは見えてこないリアルな事情もあります。
そこで役立つのがSNSや掲示板の体験談です。
実際に利用した人の声には、制度の落とし穴や見逃しがちな費用、思わぬトラブルなどが赤裸々に語られています。

ここでは、「無料だと思ってたのに違った…」というパターンや、ネット上で多く見られる誤解、そして実際に損をした・得をしたという生の声をご紹介していきます。
「無料だと思ったのに違った…」という投稿
TwitterやX(旧Twitter)で目立つのが、「〇〇支援施設、無料って聞いてたのに交通費と昼食代でけっこうかかるんだが…」という投稿です。こうした声は少なくありません。
たとえば…
-
「通所回数が少ないから工賃はほぼゼロ、それなのに毎月昼食代が5,000円超えてて地味にきつい」
-
「利用料は無料だったけど、交通費が支給されないタイプの事業所で…月3,000円以上の出費になってる」
など、“利用料は無料だけど、トータルで見たら無料じゃなかった”というケースが続出しています。
これらの投稿は「知らずに契約してしまった」パターンが多く、やはり事前のチェックや施設への確認が大切です。
掲示板で多い誤解ランキングTOP3
匿名掲示板(Yahoo!知恵袋や5ch)では、支援サービスに関する勘違いも多く見られます。中でもよくある誤解は次の3つです。
1位:「非課税世帯=一人暮らしなら全員対象」
→実際は、世帯全体の収入が基準なので、一人暮らしでも収入があると無料にならないケースがあります。
2位:「工賃があるからお金がもらえる=黒字になる」
→工賃は月1万円程度が多く、昼食・交通費の自己負担があるとむしろ赤字になることも。
3位:「手帳を持っていないと支援施設は使えない」
→医師の意見書があれば、手帳がなくても受給者証を取得して利用できるケースがあります。
こういった誤解は、多くの人が制度の全体像を把握しにくいことから生まれています。
支援施設の料金で損した・得した体験談
ネット上には「損した!」という声もあれば、「ちゃんと調べて得した」という声もあり、まさに対照的です。
【損した人の例】
-
「上限額があるのを知らずに、1万円以上支払っていた」
-
「障害者手帳を持っていたのに、自治体に申請し忘れて全額負担になった」
【得した人の例】
-
「昼食と交通費が無料の施設を選んだら、実質出費ゼロで1年間通えた」
-
「自治体の独自補助で、病院の通院費までカバーしてもらえた」
こうした体験談から見えるのは、「正しい情報に早くアクセスした人ほど得をする」という現実です。
まとめると、SNSや掲示板での声は決してバカにできません。制度の説明では触れられない「現場のリアル」が詰まっているからです。
自分がどの制度を使えるのか、どの施設が合っていそうかを調べるとき、公式情報だけでなく「利用者の声」もぜひチェックしてみて下さい。

それが、ムダな出費や後悔を減らすための近道になりますよ。
無料じゃなくても価値がある施設とは?
「無料で使える支援施設」ばかりが注目されがちですが、実際に利用した人の中には「お金を払ってでも通ってよかった」という声も多くあります。
確かに金銭的な負担は少ないほうがうれしいですが、それ以上に「安心して通える」「スタッフが親身」など、お金では測れない価値を感じている方もいます。

ここでは、あえて「無料じゃなかったけど満足している」という事例に注目し、施設選びの視点を広げてみましょう。
月3万円の負担でも「支援が手厚くて満足」の声
SNSや口コミを見ると、「月に3万円近く支払っているけど、この施設で良かった」と話す人もいます。その理由はシンプルで「支援がすごく手厚かったから」なんです。
例えば…
-
応募書類の添削を何度もしてくれた
-
面接練習の相手を本番さながらにやってくれた
-
精神的に落ち込んでいる時に、毎日のように声をかけてくれた
こういったサポートは、数字では測れませんが、再就職や生活の安定につながる大きな後押しになります。
「無料だったけど放置気味の施設」よりも、「少しお金がかかっても丁寧に関わってくれる施設」の方が、自分の人生にとってプラスになると感じる人も多いです。
お金より「居場所」「人間関係」を重視した人の選び方
「自分の居場所がほしかった」「孤独だったから誰かと関わりたかった」そう話す人も支援施設を利用しています。そういった方たちにとって、月数千円~数万円の支払いは「心の安定」を買うための投資と感じているようです。
ある人はこう語っていました。
「毎日家にいて孤独感が強くて‥。この施設に通ってから、誰かと挨拶する時間ができて、生きてる実感がわいた」
施設の質というと、就職率や訓練内容などに目が行きがちですが、「人間関係」や「過ごしやすさ」も同じくらい大切です。
支払い金額とサービスの質が必ずしも比例しない現実
「お金を出せばいい支援が受けられる」わけではありません。逆に、無料で利用できても放置される、訓練の質が低い、職員が冷たい、など残念な施設もあります。
一方で、補助が出ない地域にある私費負担の多い施設でも、利用者満足度が高いところもあります。この差は、スタッフの姿勢や、利用者との距離感に表れてきます。
だからこそ、「無料か有料か」だけで判断するのではなく、見学・体験利用を通して、実際の雰囲気を自分で確かめるのが大切なんです。
金額だけにとらわれず、「自分にとって価値のある場所か?」を見極めましょう。

たとえ無料じゃなくても、そこで得られる経験や出会いが、自分の人生にとって大きな意味を持つこともありますよ。
障害福祉サービス別|1日の利用料と自己負担の目安料金表
ここでは、障害者支援施設を利用する際にかかる1日の利用料の目安と、実際に支払う自己負担額をわかりやすく一覧にまとめました。
施設によって若干の差はありますが、だいたいの金額感を把握する参考にして下さい。
| サービス名 | 1日の利用料(全体の費用) | 利用者負担(1割目安) | 無料利用の割合(全国平均) |
|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | 5,000〜13,000円 | 500〜1,300円 | 約93.7%が無料 |
| 就労継続支援A型 | 5,000〜10,000円 | 500〜1,000円 | 約91.3%が無料 |
| 就労継続支援B型 | 5,000〜7,000円 | 500〜700円 | 約96.9%が無料 |
| 自立訓練(機能訓練) | 4,000〜10,000円 | 400〜1,000円 | 約72.1%が無料 |
| 自立訓練(生活訓練) | 5,000〜11,000円 | 500〜1,100円 | 約95.2%が無料 |
| 生活介護 | 6,000〜12,000円 | 600〜1,200円 | 約97.7%が無料 |
※料金はあくまで目安であり、実際の金額は施設ごとに異なります
※「1日の利用料」は国・自治体が9割負担し、利用者が1割を負担する仕組みです
自己負担上限額(年収・世帯構成別)
| 区分 | 対象世帯 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 所得割16万円未満(18歳以上) | 9,300円 |
| 一般1 | 所得割28万円未満(18歳未満) | 4,600〜9,300円 |
| 一般2 | 上記以外(課税世帯) | 37,200円 |

どの区分に該当するかは、市区町村の窓口や、シミュレーターを使って確認できます。
見落としやすい追加費用
利用料の他に、以下の実費負担が発生することがあります。
-
昼食代:300〜500円前後(補助ありの事業所も多数)
-
交通費:公共交通機関利用分、通所手段によって異なる
-
医療費:リハビリや訓練で医療行為を伴う場合
-
行事費:イベントや外出支援がある場合など
気になる事業所がある方は、「料金」「補助の有無」「上限額の扱い」などを見学時に必ず聞いておくと安心です。

料金で損しないためにも、納得できるまで確認しておくのがオススメですよ。
よくある質問
障害福祉サービスの利用料は本当に無料なの?
はい、生活保護を受けている方や、市町村民税非課税世帯の方であれば自己負担額が0円になるため、無料で利用できます。ただし、「自分は非課税世帯のつもりだったけど、実は対象外だった」というケースもあるので、世帯の収入や課税状況を市役所などで確認しておくと安心です。
親と同居していると無料で使えないって本当?
これはよくある誤解です。実際には「親と同居=無料ではない」場合があります。利用料の負担上限は「本人の収入」だけでなく、「同じ世帯の収入」も関係してくるからです。たとえば、親が課税対象の場合、その世帯は「非課税世帯」に該当しないため、利用料が発生することがあります。世帯分離の相談も含めて、福祉課に問い合わせるのが確実です。
サービス内容によって利用料は変わるの?
はい、支援内容や施設のタイプによって1日の利用料金が異なります。たとえば就労移行支援なら500円~1,300円、B型なら500円~700円程度が相場です。また、訓練時間や支援の手厚さによっても違いがあるので、見学や事前相談で確認するのがおすすめです。
利用料以外にかかる費用ってなにがある?
交通費、昼食代、医療費、イベント参加費などが実費でかかることがあります。ただし、自治体や事業所によっては補助制度があるので、「無料かどうか」だけでなく、「トータルでどれくらい負担があるか?」をチェックするのがポイントです。
どうやって自分の料金を計算すればいいの?
いちばん簡単なのはオンラインのシミュレーションツールを使う方法です。市区町村や施設の公式サイトにあることが多いので、「障害福祉サービス 利用者負担 計算」と検索すると見つかります。必要なのは世帯の住民税課税状況なので、家族の収入も把握しておくと正確に試算できますよ。
手帳がなくても利用できるって本当?
はい、本当です。「障害者手帳がなくても、医師の意見書があれば受給者証を取得できる」ケースがあります。とくに発達障害のグレーゾーンや適応障害など、軽度な症状でも対象になる場合があるので、まずは心療内科や精神科で相談してみて下さい。
見学や体験は誰でもできるの?
多くの施設では、受給者証がなくても見学や体験が可能です。事前予約が必要な場合が多いので、気になる事業所があれば、まずは電話やホームページから問い合わせてみて下さい。「自分に合うかどうか」は見学しないとわからないので、複数回って比較するのがおすすめです。
就労支援は何歳まで利用できる?
原則として、就労移行支援などは65歳未満が対象とされています。ただし、就労継続支援B型などは高齢でも通えるケースがあるため、「年齢でNG」とは限りません。60歳を超えている方は、事業所と市区町村の両方に確認するのが良いでしょう。
このように、障害者支援施設の利用料や制度にはいろんな疑問がつきものです。
少しでも不安があれば、地域の福祉課や施設の窓口に相談してみるのがいちばんの近道です。

無理なく安心して支援を受けるために、納得のいくまで確認してみて下さいね。
まとめ|自己負担額のルールを知れば損しない
障害福祉サービスの利用料は「1割負担」が基本ですが、年収や世帯の状況によっては「月額上限」が決まっていて、支払いが少なく済むケースが多いです。
特に生活保護や住民税非課税世帯に該当すれば、ほとんどのサービスが無料で利用できます。
知らないまま諦めていた方も、制度の仕組みを知ることで経済的なハードルを大きく下げられます。
条件に合えば、手帳がなくても無料になる場合もある
障害者手帳がなくても、医師の意見書があれば「障害福祉サービス受給者証」を取得できるケースがあります。
実際に、発達障害グレーゾーンや適応障害の方が支援を受けられた例もあります。
この受給者証があれば、利用料の減免対象になることもあり、金銭的な負担を抑えて必要な支援を受ける道が開けます。
まずは窓口相談と見学で「使える支援」を把握しよう
制度が複雑で、ネットの情報だけでは自分に当てはまるか判断しづらい部分もあります。
迷ったときは、お住まいの市区町村の福祉窓口で相談するのがおすすめです。
また、気になる事業所があれば、実際に見学してスタッフの対応や支援内容をチェックしておくと安心です。
料金の不安がある方も、見学時にしっかり確認すれば「こんなに手厚くサポートがあるなら通ってみようかな」と前向きな気持ちになれるはずです。
支援制度は“使ってナンボ”ですからね。

焦らず丁寧に、自分に合う環境を探していきましょう。