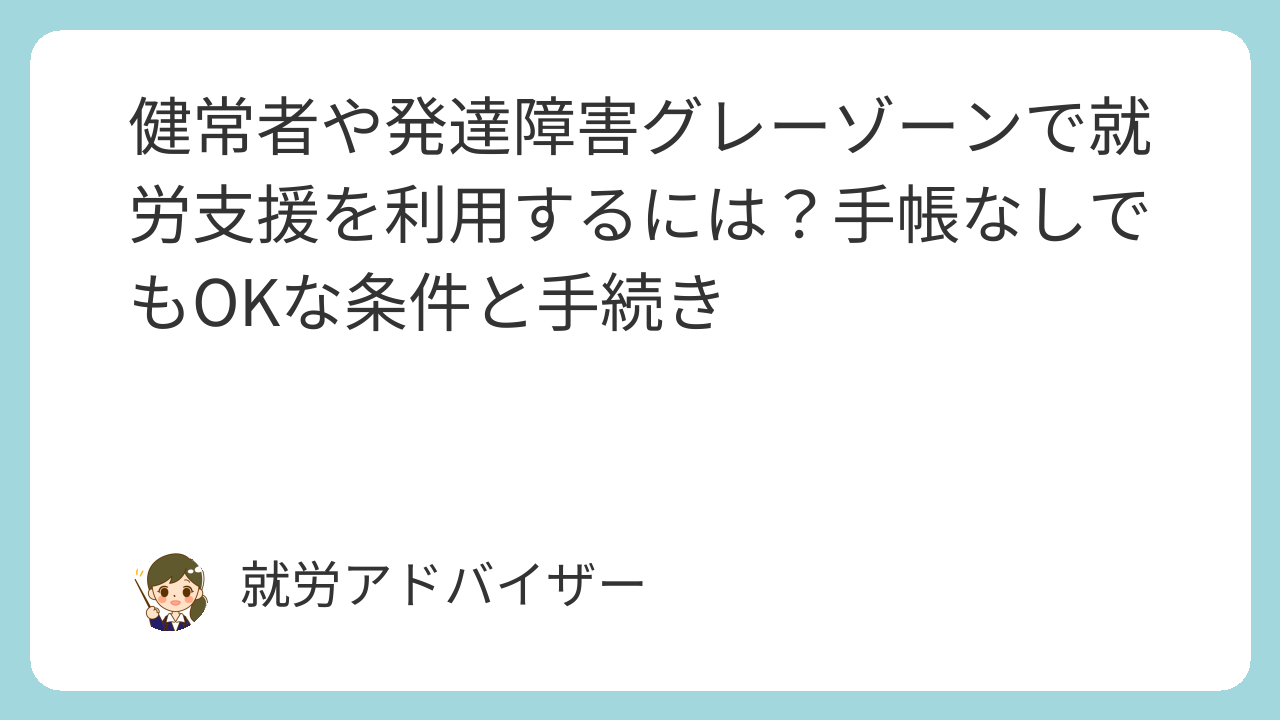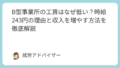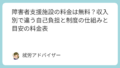就労支援サービスは、基本的に障害のある人を対象とした制度ですが、実は障害者手帳がなくても利用できるケースがあります。発達障害のグレーゾーンや、適応障害などの診断がない人でも、医師の意見書があれば支援を受けられる可能性があるため、詳しく知っておくことが大切です。
特に、「働くのがつらい」「人間関係が苦手」「ストレスがたまりやすい」などの悩みを抱えている場合は、就労支援を活用することで仕事の負担を軽減しながら、無理なく働ける環境を整えることができるかもしれません。本記事では、健常者として生活している人でも就労支援を利用する方法について詳しく解説します。
健常者でも就労支援を受けられるのか?
就労支援は基本的に障害のある人向けの制度ですが、障害者手帳がなくても支援を受けられる可能性があります。「仕事が長続きしない」「人間関係に強いストレスを感じる」「うつや不安で仕事ができない」などの悩みがある場合、医師の意見書を取得することで「障害福祉サービス受給者証」を発行してもらい、就労支援を利用できるケースがあります。
医師の意見書があれば可能なケース
就労支援を受けるために必要なのは、障害者手帳ではなく「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証は、医師の意見書があれば取得できる場合があるため、手帳を持っていない人でも利用できる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースでは受給者証が発行される可能性が高いです
✅ 発達障害のグレーゾーンと診断された人
✅ うつ病や適応障害と診断された人
✅ 強いストレスで仕事を続けるのが難しい人
✅ 対人関係が苦手で働くことがつらい人
「自分は健常者だと思っていたけれど、仕事がうまくいかない…」と悩んでいる場合でも、医師の診察を受けて意見書をもらえれば、就労支援を利用できる可能性があります。
手帳なしで受けられる支援の種類
障害者手帳がなくても、医師の意見書があれば受けられる就労支援には、主に3種類あります
① 就労移行支援(一般就労を目指す人向け)
-
対象者: 一般企業への就職を目指す人
-
支援内容: ビジネスマナー、履歴書添削、面接対策、職場体験
-
利用期間: 原則2年以内
-
メリット: 就職後も職場定着支援が受けられる
就職を目指す人に特化した支援が受けられるため、**「働く準備を整えたい」「仕事を長く続けられるようになりたい」**という人に向いています。
② 就労継続支援A型(パートタイム的に働ける)
-
対象者: 仕事をする体力があるが、一般企業で働くのが難しい人
-
支援内容: 雇用契約を結び、最低賃金以上の給与がもらえる
-
利用期間: 制限なし
-
メリット: 障害者雇用と同じような働き方ができる
就労継続支援A型では、雇用契約を結んで働くため、「最低賃金以上の給料がもらえる」のが特徴です。
③ 就労継続支援B型(短時間&マイペースに働ける)
-
対象者: 体調に合わせて少しずつ働きたい人
-
支援内容: 軽作業(シール貼り、梱包、清掃など)を行い、工賃が支払われる
-
利用期間: 制限なし
-
メリット: 自由なペースで通所できる(週1日・1時間からOK)
雇用契約を結ばないため、最低賃金の適用はなく、工賃(お小遣いのようなもの)がもらえる形ですが、通所日数や時間が自由に調整できるため、「無理なく社会参加をしたい」という人に向いています。
どの支援が自分に合っているのか?
✅ 「一般就職を目指したい!」 → 就労移行支援
✅ 「給料をもらいながら少しずつ働きたい」 → 就労継続支援A型
✅ 「体調に合わせてマイペースに働きたい」 → 就労継続支援B型
自分に合った支援を選び、無理なく仕事を続けられる環境を整えていきましょう✨
就労支援サービスの種類と特徴
就労支援サービスには大きく3つの種類があります。それぞれ特徴や対象者が異なるため、自分に合った支援を選ぶことが大切です。「一般企業への就職を目指すのか」「少しずつ働きたいのか」など、自分の目的に合わせて選びましょう。
就労移行支援とは?
就労移行支援は、「一般企業への就職を目指す人向け」の支援サービスです。
対象者
-
就職活動がうまくいかない人
-
仕事が長続きしない人
-
コミュニケーションに不安がある人
-
生活リズムを整えたい人
支援内容
-
ビジネスマナー講座(敬語・電話対応・メールの書き方)
-
コミュニケーション訓練(会話の練習・対人関係のストレス軽減)
-
PCスキル研修(Excel・Word・PowerPoint・プログラミングなど)
-
就職活動サポート(履歴書・職務経歴書の添削、面接練習)
-
職場実習(実際の企業で働く経験を積む)
利用条件
医師の意見書があれば、障害者手帳がなくても利用できるケースがあります。
利用期間
原則2年間(必要に応じて延長可)
メリット
✅ 一般企業への就職を目指せる
✅ 企業実習を通じてリアルな職場環境を経験できる
✅ 定着支援があり、就職後もサポートを受けられる
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型は、雇用契約を結んで最低賃金以上の給料をもらいながら働ける支援です。
対象者
-
体調が安定しており、継続的に働ける人
-
企業での就労が難しいが、ある程度の労働が可能な人
-
軽作業などの仕事をしながらリハビリをしたい人
仕事内容
-
軽作業(シール貼り・袋詰め・部品組み立て・データ入力など)
-
農作業(野菜の栽培・収穫・加工)
-
清掃業務(施設やオフィスの清掃)
-
カフェ・飲食業(調理補助・ホールスタッフ)
支援内容
-
働きながら生活リズムを整える
-
労働習慣を身につける
-
職場でのコミュニケーションを学ぶ
-
一般企業への転職サポートもあり
給料について
A型事業所は雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料が保証されます。地域によりますが、月7万~12万円ほどの収入になることが多いです。
メリット
✅ 働きながらリハビリができる
✅ 最低賃金が保証されている
✅ 体調が悪いときは柔軟な働き方ができる
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず、短時間勤務が可能な支援です。
対象者
-
体調に波があり、長時間働くのが難しい人
-
一般企業やA型事業所で働くのが困難な人
-
自分のペースでゆっくり社会復帰を目指したい人
仕事内容
-
シール貼りや梱包作業
-
農作業や園芸
-
パン・お菓子製造
-
リサイクル作業や清掃
支援内容
-
短時間・週1日から通所OK
-
仕事のリズムを身につける
-
無理のない範囲で社会参加できる
工賃(給料)について
B型事業所は雇用契約を結ばないため、給料ではなく「工賃(お駄賃のようなもの)」が支払われます。全国平均は月額1万7,000円・時給243円程度です。
メリット
✅ 自由なペースで通える(週1日・1時間でもOK)
✅ 体調を見ながら無理なく働ける
✅ 社会復帰のリハビリとして利用できる
どの支援が自分に合っているのか?
✅ 「一般就職を目指したい!」 → 就労移行支援
✅ 「給料をもらいながら少しずつ働きたい」 → 就労継続支援A型
✅ 「体調に合わせてマイペースに働きたい」 → 就労継続支援B型
就労支援サービスは、単に「働く場所」ではなく、無理なく社会復帰を目指すためのサポートが受けられる場所です✨自分に合った支援を選び、安心して働ける環境を整えていきましょう!
発達障害グレーゾーンでも受けられる?
発達障害の診断がなくても、医師の意見書があれば就労支援サービスを利用できる可能性があります。発達障害グレーゾーンや適応障害、HSP(繊細さん)などの人でも、一定の症状がある場合は支援が受けられるケースが多いです。
診断がなくても意見書がもらえるケース
発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の特性があるものの、診断基準を満たさず正式な診断が下りない状態を指します。診断がないからといって「生きづらさがない」わけではなく、日常生活や仕事で困難を感じている人は少なくありません。
✅ 意見書をもらいやすい人の特徴
-
過去に仕事が続かなかった経験がある
-
コミュニケーションが苦手で人間関係がうまくいかない
-
何をするにも極端に疲れやすい
-
指示をうまく理解できず、ミスが多い
-
集中力が続かず、仕事が思うように進まない
-
人の顔色をうかがいすぎて精神的に消耗する
このような症状がある場合、医師に相談すると「就労支援を受けたほうがよい」と判断され、意見書を発行してもらえる可能性があります。
意見書がもらえる症状の具体例
意見書は、単に「診断名」がついているかどうかではなく、どれだけ日常生活や仕事に影響が出ているかがポイントになります。以下のような症状がある場合、意見書を発行してもらいやすいです。
✅ 何をするにも疲れやすい
-
仕事や日常生活で異常に疲れる
-
何もしていなくても体がだるく、集中できない
-
睡眠をとっても疲労感が抜けにくい
✅ 仕事が長続きしない
-
転職を繰り返してしまう
-
職場の環境になじめず、短期間で辞めてしまう
-
仕事のミスが多く、自信をなくしてしまう
✅ 人と話すのが苦手でストレスが大きい
-
会話がスムーズにできない
-
空気を読むのが苦手で、職場で浮いてしまう
-
些細なコミュニケーションでも疲れてしまう
✅ 些細なことで緊張してしまう
-
電話対応や会議で極端に緊張する
-
初対面の人と話すのが怖い
-
何気ない日常の場面でも強いプレッシャーを感じる
このような症状がある場合、**「日常生活や仕事に困難がある」**という理由で、意見書をもらいやすくなります。
意見書をもらうためのポイント
医師に意見書をお願いするときは、自分の症状や困っていることを具体的に伝えるのが大切です。
伝え方の例
-
「仕事を始めても3ヶ月以上続いたことがない」
-
「職場の人とうまく会話できず、トラブルになることがある」
-
「疲れやすく、毎日出勤するのが負担になってしまう」
医師に「就労支援を受けたい」と伝えたうえで、現在の悩みや症状を話すと、意見書をもらいやすくなります。
意見書がもらえたらどうすればいい?
意見書がもらえたら、市区町村の障害福祉課に相談し、**「障害福祉サービス受給者証」**を申請します。これがあれば、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用できるようになります。
発達障害のグレーゾーンでも、適切な支援を受けることで働きやすくなることは十分にあります✨「診断がないから無理かも」と諦めず、まずは医師や自治体に相談してみましょう!
医師の意見書をもらう方法
就労支援を受けるためには、医師の意見書が必要になることが多いです。発達障害のグレーゾーンや適応障害、HSP(繊細さん)などで診断を受けていない人でも、医師の意見書があれば支援を受けられる可能性があります。どの診療科を受診すればよいのか、意見書の費用や発行までの流れについて詳しく解説します。
どの診療科を受診すればよい?
意見書をもらうには、精神科や心療内科を受診するのが一般的です。これらの診療科では、発達障害の検査やストレス、適応障害などの診察を行っています。
病院を選ぶときのポイント
✅ 発達障害の検査をしているか?(発達障害の専門医がいると安心)
✅ 初診予約が取りやすいか?(予約が数ヶ月待ちの病院もある)
✅ 自分の症状に合った診療を行っているか?
発達障害の検査は、大きな病院や専門のクリニックで行われていることが多いですが、地域によっては対応していない病院もあります。**「発達障害 診断 〇〇(地名)」**などで検索すると、検査可能な病院が見つかるかもしれません。
また、HSP(繊細さん)や適応障害の場合は、ストレスケア専門の心療内科が適していることもあります。
診察時に「就労支援を受けたい」ことを伝える
病院を受診したら、医師に**「就労支援を受けるために意見書が必要」**であることを伝えましょう。
伝え方の例
「仕事が続かず、就労支援を利用したいと思っています」
「コミュニケーションが苦手で、職場で困ることが多いです」
「日常生活でも疲れやすく、ストレスを感じやすいです」
医師は、患者がどれくらい就労に困難を感じているかを判断し、必要があれば意見書を発行してくれます。
意見書の費用と発行までの流れ
意見書を発行してもらうには、2,000円~5,000円程度の費用がかかるのが一般的です。これは病院によって異なりますが、健康保険の対象外となるため、自費負担になります。
意見書発行までの流れ
1️⃣ 病院の予約を取る(発達障害の検査が必要な場合、予約が混み合っていることが多い)
2️⃣ 初診を受ける(医師に症状を伝え、「就労支援を受けたい」と相談する)
3️⃣ 意見書の発行を依頼する(発行まで数日~数週間かかることもある)
4️⃣ 受け取ったら市区町村の障害福祉課へ提出する
自治体によって発行条件が違う?
自治体によっては、一定の診察期間を経ないと意見書を発行してもらえないケースがあります。例えば、初診ではすぐに意見書がもらえず、数回通院して状態を確認したうえで発行する病院もあります。
また、発達障害の診断が下りるかどうかに関係なく、就労支援の必要性が認められれば意見書を発行してもらえることが多いです。
もし「すぐに意見書が欲しい」という場合は、病院に予約を取る際に「就労支援のための意見書が必要」と伝えておくとスムーズです。
意見書をもらったら次のステップへ
意見書を受け取ったら、住んでいる市区町村の障害福祉課へ行き、「障害福祉サービス受給者証」を申請します。これがあれば、就労移行支援や就労継続支援A型・B型の利用が可能になります。
ポイント
✅ 意見書は医師によって判断が違うので、もらえない場合は別の病院でセカンドオピニオンを受けるのもアリ
✅ 意見書発行の条件は自治体ごとに違うため、事前に市区町村の障害福祉課に確認しておくとよい
✅ 受給者証の申請には時間がかかるため、早めに手続きを進めるのがおすすめ
就労支援を利用するためには、まず「意見書をもらう→受給者証を申請する」という流れが大切です。仕事に不安を感じている人は、まず医師に相談し、意見書を取得できるか確認してみましょう✨
障害福祉サービス受給者証の取得手順
就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用するには、障害福祉サービス受給者証の取得が必要です。この受給者証は、障害者手帳とは異なり、医師の意見書があれば取得できるケースもあるため、発達障害のグレーゾーンや適応障害の人も利用できる可能性があります。
ここでは、受給者証を取得するための手続きの流れや自治体ごとの違いについて詳しく解説します。
申請に必要な書類と流れ
受給者証を取得するためには、市区町村の障害福祉課で申請を行う必要があります。具体的な流れは以下の通りです
1️⃣ 医師の意見書をもらう
まず、精神科や心療内科で**「就労支援を受けたい」**と相談し、医師の意見書を発行してもらいます。意見書は診断書とは異なり、就労支援が必要であることを示すものです。
医師の意見書をもらう際のポイント
✅ 「発達障害」「適応障害」などの診断がなくても、症状があれば発行してもらえるケースがある
✅ 診察当日に発行されるとは限らず、数回通院してからの発行となる場合もある
✅ 病院ごとに対応が異なるため、事前に「就労支援の意見書を発行できるか」確認しておくとスムーズ
必要な診察費用の目安
・初診料+診察費:3,000円~5,000円程度(健康保険適用)
・意見書の発行費用:2,000円~5,000円(自費負担)
2️⃣ 市区町村の福祉課へ申請
意見書を用意できたら、住んでいる市区町村の障害福祉課へ行き、障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
申請時に必要なもの
✅ 医師の意見書(発行から3ヶ月以内のもの)
✅ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
✅ 障害者手帳(ある場合のみ)
✅ 印鑑(自治体によっては不要な場合もあり)
✅ 収入を証明する書類(非課税世帯や生活保護の場合、利用料が無料になるため)
※ 住民票が必要な場合もあるので、事前に役所で確認しておきましょう。
3️⃣ 自治体の審査を受ける
申請後、市区町村の担当者による審査が行われます。この審査では、以下の点がチェックされます
✅ 支援が必要な理由があるか(医師の意見書の内容を確認)
✅ どの就労支援サービスが適しているか(就労移行支援・A型・B型など)
✅ 世帯収入による自己負担額の決定(生活保護世帯や非課税世帯は無料)
審査のポイント
・自治体によっては、追加で面談が必要になることもある
・軽度の症状(グレーゾーンなど)の場合、受給者証が発行されない可能性もある
4️⃣ 受給者証の発行(約1ヶ月)
審査が通れば、約1ヶ月後に「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。この受給者証を持っていれば、就労移行支援や就労継続支援を利用できるようになります。
受給者証を受け取ったらやるべきこと
✅ 希望する就労支援施設に連絡し、見学や体験を申し込む
✅ 利用契約を結び、通所を開始する
✅ 負担上限額の確認(無料で利用できるかどうか)
※受給者証は1年ごとに更新が必要な場合が多いため、期限に注意しましょう。
自治体による判断の違い
受給者証の審査基準は、市区町村によって異なります。例えば、A市では軽度の発達障害の人でも支援を受けられるのに、B市では「診断名がないと不可」と言われるケースもあります。
自治体ごとの違いを確認するには?
・申請前に障害福祉課で相談する(審査基準を教えてもらえる)
・他の自治体の事例を調べる(SNSや体験談ブログも参考になる)
・発行を断られた場合は、別の病院でセカンドオピニオンをもらう
スムーズに受給者証を取得するためのポイント
✅ 医師の意見書をもらう(診断がなくても発行されることがある)
✅ 必要な書類を準備し、市区町村の福祉課で申請する
✅ 自治体の審査基準を事前に確認する(軽度の症状でも申請できるか確認)
✅ 受給者証が発行されたら、すぐに就労支援施設を探して見学する
就労支援を受けるには、まず受給者証の取得が第一歩です。「自分は対象になるかわからない…」という人も、まずは医師に相談し、意見書をもらえるか試してみることが大切です。自治体ごとに対応が違うため、事前に窓口で相談してみるのもおすすめです✨
実際に就労支援を利用するまでの流れ
就労支援を受けるには、受給者証の取得後に、自分に合った事業所を選ぶことが大切です。事業所によって支援の内容や環境が異なるため、見学や体験利用をして比較することが重要になります。ここでは、就労支援を利用するまでの具体的な流れや、事業所を選ぶ際のチェックポイントについて詳しく解説します。
見学・体験利用をする方法
受給者証を取得したら、まずは複数の事業所を見学しましょう。事業所ごとに、訓練内容や雰囲気、サポートの手厚さが違うため、見学せずに決めてしまうのは避けたほうが良いです。
見学・体験利用の流れ
1️⃣ 気になる事業所をリストアップ
「就労移行支援」「A型・B型事業所」など、希望するサービスを提供している事業所を探します。
自治体の障害福祉課の窓口や、ネット検索、口コミを参考にすると良いです。
2️⃣ 電話やメールで見学予約をする
事業所によっては「個別見学」「説明会」など、形式が異なります。
見学の際にどのようなことが知りたいか、事前にリストアップしておくとスムーズです。
3️⃣ 実際に見学・体験利用をする
訓練内容や職員の対応、利用者の雰囲気を確認します。
可能であれば1~2日間の体験利用をして、実際の支援を受けてみるのが理想です。
4️⃣ 複数の事業所を比較し、最適な施設を選ぶ
最低でも2~3カ所は見学・体験し、じっくり比較して決めましょう。
事業所選びのポイント
見学・体験利用をする際に、事業所の違いを見極めることが重要です。以下のポイントをチェックしながら、自分に合った事業所を探しましょう。
✅ 通所頻度を調整できるか?
週1日から通えるか? 体調に合わせたスケジュールが可能か?
最初は少ない日数から始め、徐々に増やせるかどうかも重要です。
✅ スタッフの対応は丁寧か?
職員の対応が冷たい、支援が事務的すぎると感じる施設は避けるべきです。
相談しやすい雰囲気かどうかも確認しましょう。
✅ どんな訓練が受けられるのか?
パソコンスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション訓練など、自分が学びたい内容があるか?
専門的なスキル(IT、デザイン、ものづくりなど)を学べるかどうかもチェック。
✅ 交通費や昼食の補助はあるか?
交通費補助があるか? 昼食の提供があるか?
金銭的な負担を減らせる事業所のほうが、通所しやすくなります。
✅ 雰囲気は自分に合っているか?
落ち着いた環境か? 利用者同士の関係性は良好か?
自分が長く通えそうな雰囲気かどうかを見極めることも大切です。
体験利用でチェックすべきポイント
実際に体験利用をするときは、以下の点を意識してみてください。
通所の負担はどのくらいか?
自宅からの距離や通いやすさをチェック
職員のサポート体制はどうか?
就職支援やメンタルサポートがしっかりしているか?
作業内容は自分に合っているか?
「思っていたよりも難しい…」とならないか確認
利用者の年齢層や雰囲気はどうか?
「若い人が多い」「シニア層が多い」など、自分に合う環境か
事業所が決まったら契約をする
事業所を決めたら、正式に契約を行います。契約時には、利用頻度・訓練内容・工賃(A型・B型の場合)などを再確認しましょう。
契約時に確認すべきこと
✅ 週何回・1日何時間通うか?
✅ 訓練のカリキュラムはどんな内容か?
✅ 自己負担額はいくらになるのか?
✅ 交通費や昼食補助はあるか?
✅ 就職支援のサポート体制はどうなっているか?
就労支援をスタート! 無理なく継続するコツ
事業所に通い始めたら、焦らず自分のペースで慣れていくことが大切です。特に、初めて就労支援を利用する人は、無理をしないようにしましょう。
無理なく継続するためのポイント
✅ 最初は短時間・少ない日数から始める(体調を崩さない範囲で)
✅ スタッフに相談しながら訓練のペースを調整する
✅ 通所がつらいときは無理せず休む(報告は忘れずに)
✅ 「就職を目指す」など目標を持つとモチベーションが上がる
就労支援を受けるまでの流れを整理しよう
✅ 受給者証を取得したら、まずは複数の事業所を見学・体験する
✅ 事業所ごとの違いをチェックし、自分に合った施設を選ぶ
✅ 通所開始後は、無理せず継続できるペースを調整する
就労支援は、単に「仕事を見つける」ための場所ではなく、自分に合った働き方を見つけ、継続できる環境を整えるための支援です。まずは気になる事業所を見学し、自分にとってベストな支援を受けられる環境を見つけてみましょう✨
手帳なしで就労支援を利用するメリット・デメリット
就労支援は、障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」を取得できれば利用可能です。ただし、自治体の判断や支援内容によっては、手帳がないことが不利になる場合もあります。ここでは、手帳なしで就労支援を利用するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット①:支援を受けながら就職を目指せる
手帳がなくても受給者証を取得できれば、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用しながら就職活動が可能です。特に、就労移行支援を利用することで、履歴書の添削や面接練習、職業訓練を受けられるため、就職の成功率が上がります。
✅ 具体的なサポート内容
履歴書・職務経歴書の作成サポート(添削・アドバイスあり)
面接練習・就職先のマッチング(模擬面接・企業紹介)
ビジネスマナーやPCスキルの訓練(MOS資格取得支援など)
職場実習の機会提供(企業でのインターンシップ)
これらの支援を無料または低価格で受けられるため、一般的な就職支援サービスよりも手厚いサポートを受けられるのが大きなメリットです。
メリット②:障害者枠にこだわらず、幅広い選択肢を持てる
手帳を持たないことで、一般枠と障害者雇用枠の両方を視野に入れた就職活動が可能になります。
✅ 障害者枠を選ばずに就職するメリット
求人の選択肢が広がる(企業の一般枠にも応募可能)
障害者枠の倍率が高い場合でも、一般枠で就職できるチャンスがある
職場で特別扱いされずに働ける(職場の理解度に左右されにくい)
特に「手帳を持つほどではないが、生きづらさがある」という人にとっては、支援を受けつつ、一般枠での就職を目指せるのは大きな利点です。
デメリット①:自治体によって判断が異なる
自治体ごとに審査基準が違うため、受給者証が取得できないケースがあります。たとえ医師の意見書があったとしても、自治体の判断次第で支援が受けられない場合があるのです。
✅ 審査基準の違いが生まれる理由
自治体ごとに「どの程度の症状なら支援が必要か?」の基準が異なる
申請者の病歴や診断名によって受給可否が変わる(軽度の場合は断られることも)
同じ症状でも「支援が不要」と判断されることがある
住んでいる自治体の福祉課で、事前に相談することが重要です。
デメリット②:手帳がないと利用できないサービスもある
障害者手帳を持っていないと、受けられない支援や優遇措置もあります。
✅ 手帳がないと受けられない可能性がある支援
障害者枠の求人(手帳が必須の企業も多い)
交通費・福祉サービスの減免(電車やバスの割引が適用されない)
障害者向けの職業訓練校(一部は手帳が必要)
たとえば、障害者雇用枠に応募しようとしても、手帳がないと応募資格を満たさないケースがあるため、支援を受けながら障害者手帳の取得も検討するのが良いでしょう。
デメリット③:就職後に職場の配慮を受けにくい
手帳がないと、職場での合理的配慮が受けづらくなることがあります。
✅ 合理的配慮の例
体調に応じた勤務時間の調整(短時間勤務や時差出勤)
業務内容の調整(苦手な業務の軽減や、適性に合った業務の提供)
休職・復職のサポート(長期休暇後の職場復帰支援)
手帳があれば、雇用側が配慮をしやすくなるため、働きやすい環境を作りやすいです。そのため、障害が軽度でも、働きやすさを重視するなら手帳の取得を考えるのも選択肢の一つです。
手帳なしでの就労支援利用を考える際のポイント
メリット
✅ 手帳なしでも受給者証があれば支援を受けながら就職活動ができる
✅ 一般枠と障害者枠の両方を視野に入れた就職活動が可能
デメリット
✅ 自治体によって審査基準が異なる(受給者証が取得できないケースも)
✅ 手帳がないと利用できない支援がある(障害者雇用枠の求人や福祉サービスの優遇)
✅ 就職後の配慮を受けにくい(手帳がないと職場の理解を得にくい)
手帳がなくても支援を受けられる可能性はありますが、自治体の判断次第で利用できないケースもあるため、事前に福祉課に相談することが大切です。就職後のサポートを考えると、障害者手帳の取得も視野に入れながら、自分に合った支援を受ける方法を探すのがベストでしょう✨
実際に利用した人の体験談
就労支援は「障害者手帳がないと利用できない」と思われがちですが、医師の意見書があれば支援を受けられるケースもあります。ここでは、実際に支援を活用して再就職や適職を見つけた方の体験談を紹介します。
健常者として働いていたけど、支援を利用したケース
30代・男性|対人ストレスで仕事を続けられなかったケース
✅ 状況
一般企業で営業職として働いていましたが、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、強いストレスを感じるようになったそうです。次第に体調を崩し、仕事を休みがちになり、最終的には退職することに。
✅ 支援を利用するまでの経緯
退職後、「また同じことになったらどうしよう」という不安が大きく、ハローワークで相談をしたところ、就労移行支援を勧められたそうです。ただ、障害者手帳は持っていなかったため、最初は「自分には関係のない支援だ」と思っていたとのこと。
しかし、精神科を受診して相談したところ、「適応障害の可能性がある」と診断され、医師の意見書をもとに障害福祉サービス受給者証を取得。無事、就労移行支援を利用できることになりました。
✅ 支援を受けて変わったこと
自分のペースで仕事を学べた(通所日数を調整しながら無理なく訓練)
職場での対人関係の対処法を学べた(ストレスを感じたときの対処法を習得)
企業実習を経て、適職に再就職できた(営業職ではなく、事務職に転向)
結果的に、人と関わる時間が少ない事務職に就職し、ストレスなく働けるようになったそうです。
✅ 体験者の声
「障害者手帳がないと利用できないと思っていたけど、医師の意見書だけでも受けられると知って本当に助かりました。再就職に向けて不安が多かったけど、支援を受けることで少しずつ自信を取り戻せたと思います。」
発達障害のグレーゾーンでも受けられたケース
20代・女性|診断はつかなかったが、支援を受けられたケース
✅ 状況
学生時代から「忘れ物が多い」「指示を理解するのが苦手」「話がかみ合わない」と言われることが多く、仕事でも「ミスが多い」「報連相ができていない」と指摘されることが増えたそうです。
自己分析をしているうちに「発達障害のグレーゾーンでは?」と疑問を抱き、心療内科を受診。診断基準を満たすほどではなかったものの、医師からは「発達特性があり、仕事で困りやすい傾向がある」と指摘されました。
✅ 支援を利用するまでの経緯
医師に相談したところ、「支援を受けたほうがいい」とのことで、意見書を書いてもらい、障害福祉サービス受給者証を申請。無事、就労移行支援を利用できることになりました。
✅ 支援を受けて変わったこと
ミスを減らすための工夫を学べた(メモの取り方や報連相のコツを習得)
発達特性に合った職業を探せた(事務職より、マニュアル化された作業のほうが合っていた)
一般枠ではなく、障害者雇用枠での就職を決意(手帳なしでも応募できる求人を紹介してもらえた)
✅ 体験者の声
「ずっと『自分が努力不足なんだ』と思っていたけど、特性によるものだと知って、すごく気が楽になりました。支援を受けることで、自分に合った仕事を探せるようになり、職場でのミスも減りました。」
健常者でも支援を受ける選択肢がある
障害者手帳がなくても、医師の意見書があれば支援を受けられるケースがある
対人ストレスや仕事のミスに悩んでいる人も、就労移行支援を活用できる
支援を受けることで、自分に合った働き方を見つけられる可能性が高まる
「自分は健常者だから…」と諦める前に、一度、医師や自治体に相談してみることをおすすめします。適切な支援を受けることで、仕事の悩みを軽減し、無理なく働ける環境を見つけることができるかもしれません✨
まとめ
手帳がなくても、医師の意見書があれば就労支援を受けられる可能性があることがわかりました。特に発達障害のグレーゾーンや、強いストレスや疲れやすさを感じている人は、医師に相談することで「障害福祉サービス受給者証」を取得できる場合があります。
就労移行支援や就労継続支援を活用することで、自分に合った働き方を見つけ、無理なく仕事を続ける環境を整えることが可能です。手帳がなくても支援を受ける選択肢があるため、まずは心療内科や精神科を受診し、意見書がもらえるか相談してみることが大切です。
自分に合う仕事や職場環境を見つけるためにも、一歩踏み出して情報収集をし、必要な支援を受けていきましょう✨