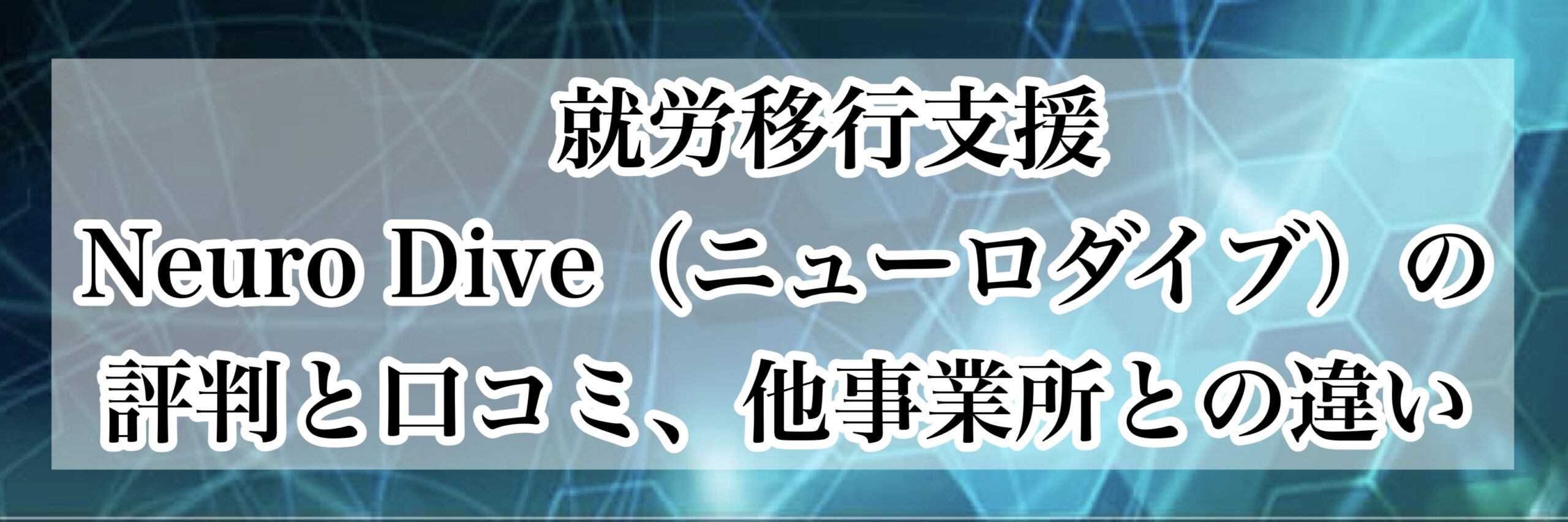発達障害や精神障害を抱える方々にとって、一般企業への就職や継続勤務には専門的な支援が欠かせないケースが多く、就労移行支援事業所はその架け橋となる存在です。
その中でも「Neuro Dive(ニューロダイブ)」は近年注目を集めており、利用者数の増加とともに口コミや評判も広がりを見せています。
ニューロダイブは一般的な就労支援に加え、発達障害特性を持つ人の強みを活かす独自の支援スタイルを打ち出しています。
従来の事業所では「できない部分を補う」ことに重点が置かれることが多かったのに対し、ニューロダイブは「個々の強みを最大化して就労につなげる」という前向きな支援方針を掲げており、その姿勢は利用者から高く評価されています。
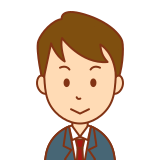
近年は自治体や企業からの注目も集まり、社会的にも重要な役割を担う存在になりつつあります。
Neuro Dive(ニューロダイブ)の口コミ・評判のリアルな声
ニューロダイブを利用するかどうかを検討している人にとって、もっとも参考になるのはやはり実際の利用者やその家族の声です。
公式サイトやパンフレットでは「理念」や「プログラム内容」が中心に紹介されていますが、実際に通所してみないと見えてこない部分も多くあります。
そのため、口コミや評判は利用を考えている人にとって重要な情報源になります。
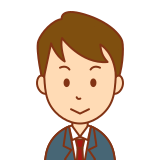
悪い口コミと良い口コミの両方を整理し、さらにSNSや掲示板でのリアルな声を紹介していきます。
ニューロダイブの悪い口コミ・評判|合わない人の実際の体験談
ニューロダイブに関する悪い口コミで多く見られるのは「合う人と合わない人がはっきり分かれる」という点です。
例えば、「自分は事務作業を希望していたが、紹介されたのは接客業中心でミスマッチを感じた」「支援員との相性が良くなくて、相談しても納得できる回答が得られなかった」という声があります。また「利用者の人数が多く、一人ひとりへの対応が薄く感じた」「オンライン支援が導入されているものの、やはり通所前提で進められる場面が多くて利用が難しかった」という不満も報告されています。
さらに、「期待していたほど企業連携が多くなかった」「実習先が限られていて選択肢が狭い」といった体験談もあり、利用するエリアや時期によって差が出ることも指摘されています。
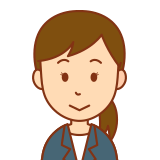
つまり、ニューロダイブがすべての人に完璧に合うとは限らず、事前に見学や相談を重ねて自分に合うかどうかを見極めることが重要だといえます。
ニューロダイブの良い口コミ・評判|スタッフ対応や雰囲気について
一方で、ポジティブな口コミでは「スタッフの対応が丁寧で安心感がある」という評価が目立ちます。
利用者からは「話を最後まで聞いてくれる姿勢が嬉しかった」「自分の特性を否定せず、強みとして伸ばそうとしてくれた」という声が多く寄せられています。
また「雰囲気が落ち着いていて通いやすい」「同じような悩みを持つ仲間と出会えて心強かった」といった感想も見られ、安心できる居場所としての役割を果たしている面もあります。
さらに「自己分析が深まり、自分がどんな職場に向いているか分かるようになった」「就職活動を伴走してもらえたおかげで不安が減った」といった実用的な評価もあります。
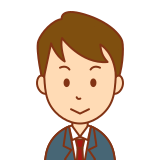
特に、発達障害や精神障害を持つ人が「就職したあと続けられるかどうか」に悩む場面で、ニューロダイブの定着支援は高く評価されています。
掲示板・SNSで見られるニューロダイブの生の声
掲示板やSNSには、公式の情報やレビューサイトには載らないリアルな声が投稿されています。
例えば、X(旧Twitter)では「ニューロダイブに通い始めて3か月、少しずつ生活リズムが整ってきた」「就労実習の面接で緊張したけど、支援員さんが同席してくれて助かった」といったポジティブな報告があります。
その一方で「思っていたよりもプログラムが一般的で、もっと専門的な訓練を期待していた」「同じ事務作業の練習ばかりで飽きてしまった」といった不満も発信されています。
掲示板では「企業とのマッチングに力を入れているのは良いが、紹介先が限られる地域もある」「人気が出てきて予約が取りにくい」という現実的な意見が多く見られます。
また「ニューロダイブに合わなかったから別の就労移行に移った」というケースも書き込まれており、利用者の体験は多様であることが分かります。
SNSや掲示板はあくまで個人の体験談であり、全員に当てはまるとは限りません。
しかし「現場の空気感」や「通っている人の生の悩み」を知るには非常に役立ちます。
こうしたリアルな声を参考にしつつ、実際に自分で見学や相談をして判断することが、最も納得感のある選択につながります。
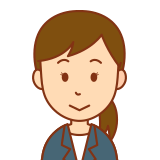
👉 ニューロダイブの口コミは「合う人にはとても合うが、合わない人もいる」という二極化した傾向が明確です。
Neuro Dive(ニューロダイブ)のデメリットとメリット
利用を検討する際には、いいところだけでなく限界や注意点をきちんと知っておくことが、期待と現実のギャップを減らすうえで重要です。
ニューロダイブを使ううえで典型的に挙げられるデメリットとメリットを比較視点も交えて解説します。
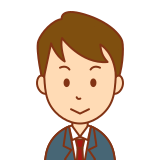
また、他の就労支援事業所と比べたときの視点を示すことで、自分に合った選択肢を見極めていきましょう!
ニューロダイブのデメリット|地域や利用制限の課題など
ニューロダイブは非常に魅力的な支援理念や先端IT分野への特化性がウリですが、その反面、使う上で注意しておきたいデメリットも存在します。
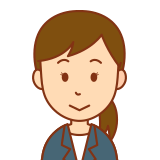
口コミ・業界情報・支援制度の観点から整理した典型的な課題です👇
1. 地域によっては通所できない・拠点が少ない
ニューロダイブは東京・横浜・大阪・福岡といった主要都市に拠点を持っていますが、それ以外の地域、特に地方・中部・北陸・四国などでは事業所がなく、通所が物理的に難しいという声があります。
また、拠点が遠い場合、通所時間や交通費が負担になることが口コミで指摘されています。
2. 利用条件・制度の制約
就労移行支援という制度上、18歳~64歳など年齢要件、障害福祉サービス受給者証の保有、離職中であることなど条件を満たす必要があります。
これらをクリアできない場合、無料サービスの対象外になる可能性があります。
また、利用対象となっても「通所できる身体的・精神的な余力」が求められるため、状態変動のある人にとっては継続が難しいケースもあります。
3. プログラム難易度・期待とのギャップ
ニューロダイブは先端IT・データサイエンス分野に特化しており、教材や講座は高度な内容を含みます。
未経験者でも学べるとはいえ、学習負荷が高いことを「ついていけない」と感じる人もいます。
実際、体験講座で入所適性を確認する仕組みがあり、自己学習力や“自走力”を重視する設計になっています。
この点が、期待していたよりも「専門性・スピード」が高く、ついていけなかったという否定的な体験につながる場合があります。
4. 選択肢やマッチングが限定される地域差
事業所が都市部中心で、そこでつながっている企業ネットワークも地元中心であることが多いため、その地域での実習先・就職先の選択肢が狭まるという声があります。
拠点間で提携先が異なるため、ある地域では強い支援が得られても、別地域では紹介力が弱い可能性があります。
加えて、支援の混み具合・定員制限により見学待ちや利用開始のタイミングが遅くなることも指摘されています。
5. 支援対象者との相性・支援体制の偏り
個別支援を掲げていても、利用者の数や支援員の人数・質によっては、対応が十分でないと感じるケースもあります。
支援員との相性問題、支援方針の違い、相談頻度の制限などが不満として上げられることがあります。
また、IT特化型であるため、ITに強みがない人や興味が薄い人にはマッチしづらい可能性があります。
メリット|専門的なサポートと個別最適化など
デメリットを理解したうえで、ニューロダイブが多くの利用者から支持される理由を、具体的な強みとともに整理します。
これらは、他事業所との差別化要素としても重要です。
1. 先端ITスキルを学べる専門支援体制
ニューロダイブは、AI、機械学習、デジタルマーケティング、可視化(BIツール)、RPA/業務効率化といった先端分野に特化したカリキュラムを提供しています。
実データを使った演習や実務に近い成果物作成、企業実習もプログラムに組み込まれており、ただ座学をこなすだけでなく実践力を磨く設計です。
2. 個別最適化された学習設計
ITアドバイザーが個々の適性・目標をもとに学習プランを設計し、5,500以上の講座から必要な100講座程度を組み合わせて進めるという柔軟性を持たせた支援体制も特徴です。
また、体験講座で入所適性を確認する制度により、ギャップを抑える工夫をしているという報告もあります。
3. 就職支援と定着支援の一貫フォロー
ニューロダイブは、単にスキルを提供して就職させるだけでなく、入社後のフォロー(定着支援)まで視野に入れた支援を重視しています。
理念に「長く働き続ける」ことを掲げており、就職先との調整支援・相談体制も整えているという説明があります。
また、自治体・企業連携を強化し、利用者
が職場で力を発揮できるよう業務設計や環境調整を提案するケースもあります。
4. 高い定着率・就職実績の報告
公開されている情報によれば、ニューロダイブは定着率が非常に高いという記載が見られます。
2022年12月の時点では「96.9%の定着率」という数字が示されています。
また、ITスキル分野での就職率も高めで、先端分野への就職成功例も多数報じられています。
5. 将来性・差別化戦略としての強み
社会的にDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI活用が進む中で、ITスキルを持つ障害者人材を育成するというコンセプトは、将来的な社会・企業ニーズにもマッチする可能性があります。
つまり、他の一般的な支援型では得にくい「希少性のある能力」を獲得できる可能性があります。
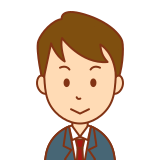
さらに、オンライン学習サービス「Neuro Dive Online」を設けることで、通所できない人にも学習機会を開放しており、柔軟性を持たせている点も強みです。
他の就労支援事業所との比較視点
ニューロダイブを選ぶかどうかの判断材料として、他の就労移行支援事業所と比較する観点を持つことが大切です。
以下は、比較上注目すべきポイントと、ニューロダイブの立ち位置を整理した視点です。
| 比較要素 | 他の典型的な支援事業所 | ニューロダイブの強み・注意点 |
|---|---|---|
| 支援対象の広さ | 多様な障害・多分野に対応(身体・知的・精神など) | 発達障害・精神障害・知的障害も対象だが、IT特化型であるため興味・適性が問われる |
| プログラムの汎用性 vs 特化性 | 総合型支援で幅広い職種に対応 | IT・DX・AI分野に特化し、強みを磨く設計 |
| 拠点数・通いやすさ | 全国網羅型の事業所(例:LITALICOワークスなど) | 都市部中心、地方では通所が難しい可能性あり |
| マッチング企業ネットワーク | 地方企業・地域密着型企業との提携が多い | IT企業との提携や先端分野重視。地域による提携格差あり |
| 難易度・負荷 | 比較的基礎レベル~幅広いレベル対応 | 高度な専門性を要求されることがある |
| 定着支援・アフターケア | 支援体制は事業所ごとに差がある | 定着支援にも力を入れており理念で掲げられている点が強み |
| オンライン対応 | 通所中心が多いが近年リモート対応も拡大傾向 | オンライン学習サービスを併設し柔軟性を持たせている |
比較視点から言うと、次のようなケースでニューロダイブが特に有利・あるいは適さない可能性があります。
-
有利なケース
・IT・DX・データ分析分野に興味や適性がある
・自己学習意欲があり、高度なスキル習得を目指したい
・住んでいる地域が拠点圏内、またはオンライン利用可能な環境がある
・将来性を見据え、差別化できるスキルを求めている -
不利または慎重なケース
・通所が難しい地域に住んでいる
・ITへの興味が薄い、または専門性がマッチしない
・体調・学習能力の波が激しく、連続した学習が難しい
・他の事業所の方が地元企業とのマッチング力に秀でている可能性がある
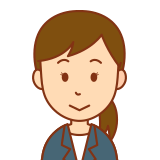
このように、ニューロダイブには明確な強みがありつつ、使うには向き・不向きがあります。
Neuro Dive(ニューロダイブ)への様々な視点
ニューロダイブはITやデータ分野に特化した就労移行支援として注目されていますが、その評価は一枚岩ではありません。
就労支援は人それぞれの状態や目的、価値観に強く左右されるため、良いと感じる人もいれば「合わなかった」と感じる人も存在します。
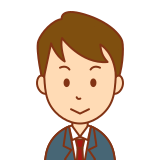
そこで、一般的な評価だけでなく、あえて異なる視点を取り入れ、ニューロダイブを多面的に考えるための材料を確認していきましょう。
「支援を受けすぎない方が自立につながる」という考え方
就労支援事業所は支援を提供することが役割ですが、ある利用者や専門家の中には「支援を受けすぎることで逆に依存してしまい、自立の妨げになる場合がある」と指摘する声もあります。
ニューロダイブは丁寧なサポートを特徴としていますが、それゆえに「自分で考える力を育てにくい」と感じる人もいます。
例えば「相談すれば支援員がすぐに動いてくれるから、自分で交渉する力が身につかなかった」「企業への調整もすべて任せきりになってしまった」という口コミもありました。
実際の就労現場では、自分で問題解決する力が求められることが多いため、過度に手厚い支援が必ずしも全員にとってプラスになるとは限りません。
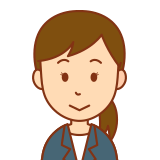
就労支援の本質は「自立を助ける環境を作ること」であり、支援の量や質のバランスを自分で考えながら調整する意識が求められるといえるでしょう。
私の主観で見たNeuro Dive利用の印象
私自身が見学したり利用者の体験談を聞いた印象では、ニューロダイブは「安心できる場所」と「挑戦できる場所」の両方を兼ね備えていると感じます。
スタッフは穏やかで話を聞いてくれる人が多く、雰囲気も落ち着いているため、初めて就労支援を利用する人でも安心して足を運びやすい空気があります。
その一方で、提供されるカリキュラムはITスキルやデータ分析など先端分野に踏み込んでおり、「学ぶ姿勢がなければ取り残される」と思わせる緊張感もあります。
つまり、居心地の良さと挑戦の厳しさが同居している場所というのが私の率直な印象です。
向上心がある人にとっては「背中を押してくれる場所」ですが、のんびり進めたい人にとっては「厳しさを感じる場所」にもなり得ると感じました。
他の事業所の方が良いと感じたケース
ニューロダイブは強みがはっきりしている分、相性が合わない人もいます。
例えば「事務職や軽作業を希望していたが、ITスキルに重点を置くニューロダイブでは学ぶ内容が合わなかった」「学習ペースが速すぎてついていけず、結局LITALICOワークスのように幅広い職種に対応している事業所の方が合っていた」という声があります。
また、地域によってはニューロダイブよりも地元企業とのつながりが強い事業所の方が就職実績につながりやすい場合もあります。
特に地方在住者にとっては「拠点が遠い」「通所に時間がかかる」などの理由から、地域密着型の事業所を選んだ方が現実的なこともあるでしょう。
さらに「ニューロダイブの専門性は魅力的だが、もっと柔軟にいろいろな業務を体験したい」という人にとっては、総合型の就労移行支援事業所の方が適しているケースもあります。
ニューロダイブは「ITに特化した専門的支援」という強い個性を持つため、適性がある人にとっては非常に魅力的ですが、そうでない人には逆に負担や不一致を生む可能性があります。
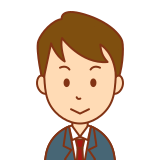
だからこそ、事前に複数の事業所を見学し、自分の将来像や特性と照らし合わせながら選ぶことが重要です。
Neuro Dive(ニューロダイブ)と他サービスの比較
Neuro Dive は専門スキル重視型の就労移行支援としてユニークな位置づけを持ちますが、他の制度・サービスと比較することで、その強み・弱み・選択基準が鮮明になります。
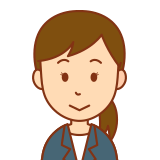
LITALICOワークスとの違い、就労移行支援と就労継続支援B型との違い、民間スクールとの比較 をしていきます!
LITALICOワークスとの違い
共通点:障害福祉制度下での就労支援
まず、Neuro Dive も LITALICOワークス も、障害福祉サービス制度(就労移行支援)を活用する枠組みに属しています。
つまり、障害福祉サービス受給者証を使って支援を受けられるという点では共通です。
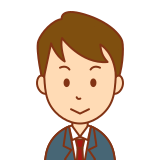
ただし、運営方針・特色・支援スタイルに違いがあります。
運営・ブランド力・拠点展開
-
LITALICOワークスは、障害者支援分野において長年の実績とブランド力を持っており、全国各地に多くの事業所を展開しています。
-
一方、Neuro Dive は比較的新しい専門型支援を標榜しており、特に IT・データ分析・DX 関連分野に特化した支援を打ち出している点で差別化を図っています。
-
LITALICO ワークスは「幅広い職種・多様な支援プログラム」を揃えており、支援対象の裾野が広いという利点があります。
支援スタイルと専門性
-
LITALICO ワークス は比較的「総合型就労移行支援」に近く、事務、接客、軽作業、オフィスワークなど多ジャンルを扱う傾向があります。
-
これに対し、Neuro Dive は「専門性を武器にする」ことを重視し、IT/Web系、データ処理/分析、DX関連技術など、より高度・先端分野を訴求する傾向があります。
-
つまり、LITALICO ワークス は「幅」で勝負、Neuro Dive は「深さ」で勝負、という構図が見られます。
就職実績・定着率
-
LITALICO ワークス は就職・定着実績の数字も公表しており、定着率で 90% 前後という報告が見られます。
-
Neuro Dive も高い定着率・成功例をアピールする声があり、IT 特化型だからこそ高待遇・リモート就業例も紹介されることがあります。
-
ただし、実際に拠点地域や企業マッチング力によって実績に差が出やすい点は、両者とも留意点です。
利用者維度・適合性
-
多様な職種志向の人や、IT に対して強い興味・経験がない人にとっては、LITALICO ワークス の幅広い選択肢が安心感となるでしょう。
-
一方、IT や専門スキルを武器にしたい人、将来的にDX・データ分野で働きたい人には、Neuro Dive の専門性重視アプローチがマッチする可能性が高いです。
まとめると、LITALICO ワークス は「オールラウンド型支援」で、Neuro Dive は「選ばれし専門型支援」という対比構造が見られます。
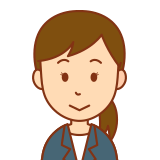
両方を見学・比較して、自分の適性と志向性に合う方を選ぶことが望ましいです。
就労移行支援と就労継続支援 B型との違い
支援制度そのものを理解することは、Neuro Dive を使うかどうかだけでなく、「どの制度枠が自分に合うか」を判断するうえで不可欠です。
以下に主な違いを整理します。
| 項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援 B型 |
|---|---|---|
| 目的 | 一般企業への就労を目指す | 一般就労が難しい人に「働く場」を提供 |
| 利用対象 | 一般就労が可能な見込みのある人 | 雇用契約を結ぶことが難しい人 |
| 雇用契約 | 基本的には支援期間中は雇用契約なし | 原則雇用契約なし |
| 工賃・給料 | 工賃は支給されない(訓練的性質) | 工賃として収入あり(低額なことが多い) |
| 利用期間制限 | 最大2年など上限があるケースあり | 上限なし(長期的な利用可) |
| 勤務形態 | 実習・企業マッチング・定着支援あり | 生産活動に重きを置き、勤務時間や働き方は比較的柔軟 |
就労移行支援は「就労可能性を引き上げて企業に送り出すこと」が目的なので、訓練・就活支援・定着支援が中心になります。
一方、就労継続支援 B 型は就労移行支援を使えない・使いにくい人(体調不安定・就労経験少ないなど)に「働く機会」を提供する福祉色の強い支援形態です。
この違いから言えること👇
-
体調が不安定で長時間通所が難しい人は、まずは B 型を利用して働く習慣をつけながら体調を安定させ、その後移行支援を目指す選択肢もあります。
-
就労移行支援はある程度通所できる・訓練が可能な状態の人に適しており、Neuro Dive はこの枠組みを最大限に活用し、専門スキルを伸ばす道を提供しています。
-
「一般就労→継続就労」まで見据える場合、移行支援で能力を高めつつ、定着支援をしっかりチェックすることが重要です。
民間スクールとの比較
Neuro Dive や就労移行支援事業所と比べて、民間スクール(プログラミングスクール、データ分析スクール、Web デザインスクールなど)は性質が異なります。
比較するポイントと判断軸を整理します。
目的・ゴールの違い
-
民間スクールは「技術習得」や「転職支援」目的が強く、受講生は対価を払ってスキルを学ぶことが中心です。
-
対して、Neuro Dive 等就労支援事業所は福祉支援制度の枠組みを使い、スキル習得+企業マッチング+定着支援まで一貫して支援する点が異なります。
費用・支援負担
-
民間スクールは基本的に自己負担(受講料が発生)します。そのため、コスト・リスクが利用者にかかる場合が多いです。
-
就労移行支援制度を使えば、受給者証を通じて公的補助でサービスを受けられることがあり、受講料負担が軽くなる可能性があります。
支援内容・補助機能
-
民間スクールは技術教育が主軸であり、メンタルケア・障害特性対応・生活リズム調整・就職定着支援まではカバーしないケースが多いです。
-
一方、Neuro Dive は障害者雇用の知見・支援ネットワーク・定着支援など、福祉的な側面まで含めたサポートが可能性があります。
マッチングと実務体験
-
民間スクールでは企業紹介を行うところもありますが、障害特性に合わせたマッチングや環境調整支援が手厚いとは限りません。
-
Neuro Dive は企業との提携・環境調整・支援員の働きかけを通じて、利用者と企業をつなぐ活動を強みとしています。
リスクと保証
-
民間スクールでは「スキルを得たが就職できない」というリスクもあります。
-
就労移行支援では、就職後定着支援を通じて「辞めない・続ける」までフォローする制度が敷かれている点がアドバンテージです。
適合性・選択基準
-
既にIT や Web に関心・素養があり、「短期間で技術を身につけたい」という強い動機をもつ人には、民間スクールで専門スキルを集中して学ぶ道も有力です。
-
ただし、障害特性や体調変動、就労継続性を重視するなら、Neuro Dive のような支援機構を使える事業所と併用・比較検討するのが賢明です.
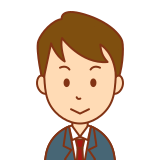
この比較を通じて伝えたいことは、Neuro Dive は 「専門性 × 就職支援制度」 を組み合わせたユニークな立ち位置を持っており、他サービスとの比較を通じてその適性を見極めることが重要だという点です。
Neuro Dive(ニューロダイブ)で提供される主なプログラム
Neuro Dive は「発達障害や精神障害を抱える方が、先端 IT 分野で働く力を身につける」ことを目的とした就労移行支援事業所です。
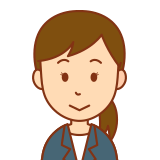
公式サイトや関係インタビューをもとに、提供されるプログラムの構成・内容、支援の方法論、個別支援計画の立て方などを見ていきます。
就労移行支援プログラムの内容
Neuro Dive の就労移行支援プログラムは、IT × ビジネススキル × 実践体験を組み合わせた構成になっています。
主な特徴と日常の流れを以下に整理します。
4 つの専門領域で学ぶ
Neuro Dive では、受講者が自らの適性・興味に応じて下記の 4 分野から学びを深めていく形を採っています。
| 領域 | 内容の一例 |
|---|---|
| AI・機械学習 | Python・統計・モデル構築・予測分析など |
| デジタルマーケティング | アクセス解析、広告運用、施策立案などのデータ活用手法 |
| ビジュアライズ | BIツール(Tableau、Power BI など)を使った可視化・ダッシュボード設計 |
| 業務効率化(RPA/改善) | ツールを用いた業務自動化、既存業務フローの改善提案など |
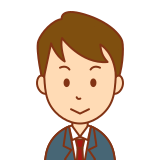
これらの分野を通じて、座学だけでなく実践課題や成果物作成まで含めた学習が行われます。
1日のカリキュラム例と時間割
Neuro Dive の日々の学習スケジュールは以下のように構成されていることが公式情報で示されています。
-
午前(10:00〜12:00頃)
– 朝のあいさつ・連絡タイム(チャットや支援員とのすり合わせ)
– ビジネス系スキル講座(コミュニケーション、セルフマネジメント、ストレス対処法など)
– グループワーク・講座形式学習 -
午後(13:00〜16:00頃)
– 各自の IT 学習(プログラミング、分析、可視化など)
– 個別面談や支援員との相談時間
– 課題演習・実践型ワーク
このように、午前はビジネス基礎と対話・調整、午後は技術学習と実践という構成で、一日の流れが定まっています。
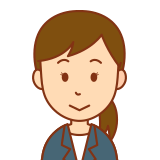
また、プログラムは 通所・オンライン併用型 で提供されており、通所が難しい場合でもオンラインで参加できるような環境が整えられています。
体験講座と入所適性確認
先端 IT 分野という専門性の高さを踏まえ、Neuro Dive では 体験講座 を設けており、入所前に受講者の適性を確認するプロセスがあります。
体験講座は数日(例:3 日間にわたるもの)行われ、技術理解・環境操作・成果物作成などを試す内容となっており、これで「自走力(自己学習力)」をある程度測るという説明があります。
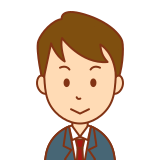
このような入所前チェックによって、入所後とのミスマッチを減らす工夫がなされている点が、Neuro Dive の特徴と言えます。
キャリア支援とスキルトレーニング
プログラム内容だけでなく、キャリア支援・実践的支援を組み込む設計が、Neuro Dive の強みのひとつです。
実践型成果物づくり・ポートフォリオ作成
学習した内容を単なる知識にとどめず、「企業に提示できるレベルの成果物」 を作ることを目標とする設計です。
企業訪問や説明会の場で、受講者が自らの成果を発表する機会も設けられており、これが就活時のアピール材料になるという実践重視の姿勢があります。
企業実習・インターン機会
Neuro Dive は、支援先企業との連携による 企業実習 を通じて現場の感覚を体験する機会を提供しています。
この実習を通じて、受講者は実際の業務環境を肌で感じながらスキルを応用・調整し、支援員と企業をつなぐフィードバックを受けながら自己理解と適応力を高めます。
就職支援(応募・面接・調整)
学習支援だけに留まらず、履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接対策、支援員との面談、応募先企業との調整支援など、就職活動支援 も包括する体制が整えられています。
さらに、就職後も 定着支援 を行うことで、就職できることだけでなく、長く継続して働ける環境づくりを支援しています。
実績として、Neuro Dive 渋谷では IT 職種就職率 86%、職場定着率 97%という数値が公表されています。
オンライン支援・Neuro Dive Online
通所が難しい受講者のために、Neuro Dive は オンライン学習プログラム「Neuro Dive Online」を併設しています。
このオンライン版は、就労移行支援制度ではない一般向けの形態も含み、時間・場所を問わず学びを継続できるようになっており、通所が難しい地方在住者や継続学習希望者にも開かれた選択肢を提供しています。
個別支援計画の立て方
就労支援事業所で重要な要素の一つに 個別支援計画(個別支援計画書、支援プラン) があります。
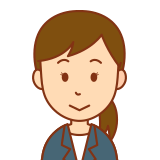
Neuro Dive における個別支援計画の立て方について、求人情報や運営者の説明をもとにまとめました👇
支援責任者の役割と計画作成業務
Neuro Dive の事業所(たとえば秋葉原拠点)では、支援責任者が 個別支援計画の立案および実行管理 を担うポジションの求人が出されており、支援計画作成が運営業務に含まれています。
この求人情報からも読み取れるのは、個別支援計画は単なる形式書類ではなく、現場で動かす“指針”として設計されている点です。
個別支援計画策定の流れ・要点
個別支援計画は、利用者の特性・希望・現状をふまえて「いつまでに」「どのスキルを」「どのように学ぶか」を設計するロードマップです。
Neuro Dive における設計要点は以下のように考えられます👇
-
現状把握と目標設定
利用者が得意な分野・興味・キャリア希望を丁寧にヒアリング
技術理解度や学習ペース、通所可能時間などの実務的制約を確認 -
専門領域選定と学習項目の抽出
前述の 4 分野(AI、デジタルマーケ、ビジュアライズ、業務効率化)から、適性と志向に応じて主軸を決定
選定後、その領域で必要な教材や演習課題を洗い出す -
学習スケジュール設計
日次/週次スケジュール(午前・午後枠など)を設計
進捗確認・調整用の個別面談時間を確保 -
成果物目標と企業実習計画
何を成果物とするか(分析レポート、可視化ダッシュボード、改善提案など)
企業実習のタイミングと目的を定め、支援員と企業との調整を盛り込む -
リスク管理・フォロー体制
体調変動や学習停滞時の調整余地を入れておく
定期的な振り返り・見直し面談を計画
定着支援も見据えて、就職後フォロー計画を事前に想定
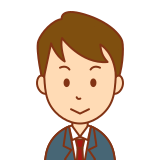
このように、個別支援計画は「変化可能な設計」であることが理想で、受講者の学びのペースや課題に応じて見直すべきものです。
運営側の教材選定とカリキュラム調整
Neuro Dive は、Udemy の講座ラインナップをベースに教材を選定し、独自のカリキュラムマップを構築しているとの説明があります。
つまり、個別支援計画では「既存の講座群から、その人に必要なものを組み合わせ、進行順序を設計する」ことが現実的な進め方です。支援責任者や IT アドバイザーがこの選定を担います。
Neuro Dive(ニューロダイブ)の概要
ニューロダイブは、株式会社 LITALICO(リタリコ)が運営する就労移行支援事業所のひとつです。
LITALICOは障害福祉分野で幅広い事業を展開している企業で、発達障害児の教育支援や就労支援サービスを中心に全国展開していることで知られています。
その中でニューロダイブは、発達障害や精神障害を持つ方に特化した就労移行支援を行い、企業と利用者をつなぐ「架け橋」として機能しています。
一般的な就労移行支援事業所と比較してニューロダイブがユニークなのは、徹底した個別対応と企業連携の仕組みを整えている点です。
利用者一人ひとりの特性を科学的に分析し、職場で発揮できるスキルを重点的に伸ばすプログラムを提供しているため、「自分に合った職場が見つかった」という声も多く寄せられています。
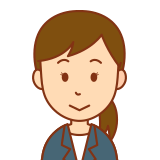
また、企業とのマッチングを積極的に支援し、就職活動の段階から入社後の定着支援まで一貫してフォローする体制を持つことも特徴です。
運営母体と設立背景
ニューロダイブを運営する株式会社 LITALICO は2005年に設立され、障害福祉領域を専門に展開してきた企業です。
教育分野では「LITALICOジュニア」、就労支援では「LITALICOワークス」などを展開し、2020年代以降は障害者雇用の拡大に対応する形でニューロダイブを立ち上げました。
背景には、日本国内で増加している発達障害や精神障害の診断数の上昇、そして企業側が人材確保と多様性対応を迫られている現状があります。
とくに発達障害を持つ人は、認知特性や行動特性によって従来の就労支援では対応が難しいケースも多く見られます。
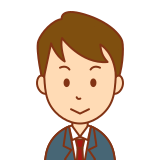
ニューロダイブは「障害=弱点」という固定観念を打破し、強みを活かす形で社会に参画できる仕組みを提供することを目的に誕生しました。
事業のミッションと理念
ニューロダイブの理念は「誰もが自分らしく働ける社会をつくる」というものです。
従来の就労支援では「社会に合わせる」ことが優先されがちでしたが、ニューロダイブは「社会が多様な個性を受け入れる」方向に舵を切っています。
具体的には、利用者の強みや得意分野を分析したうえで職業選択を行い、企業にはその人の特性に合わせた業務設計や職場環境の調整を提案します。
これは「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という概念に基づいたアプローチで、世界的にも注目を浴びている人材活用の考え方です。
また、ニューロダイブでは「就職すること」だけをゴールにせず、「長く働き続けること」を重視しています。
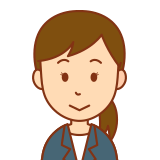
そのため、内定獲得だけでなく入社後のフォロー体制も整え、安定した就労定着を支援する仕組みを導入しています。
全国の拠点数とエリア展開
ニューロダイブは首都圏を中心に全国展開を進めています。
2025年現在、東京・神奈川・大阪・愛知といった主要都市に事業所を設置しており、今後も需要の高まりに応じて拡大予定です。
地域によってはまだ事業所が少ないため、利用を希望しても通所が難しいケースもありますが、オンライン支援の導入によって地方在住者にもサービスを提供できるよう体制を整えています。
このため「地理的な制約で利用できない」という課題を減らし、全国規模での支援を可能にしています。
また、ニューロダイブは各事業所ごとに地域企業とのネットワークを構築しており、地域に根ざした就職支援が実現しているのも特徴です。
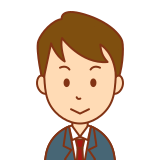
たとえば東京エリアではIT企業や大手メーカーとの提携、大阪エリアではサービス業や物流企業との連携といった形で、地域ごとの産業構造に合わせた就労支援を展開しています。